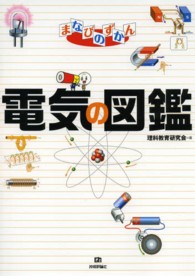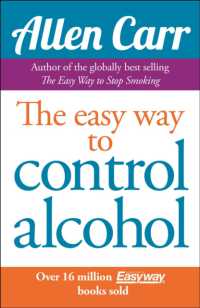内容説明
船乗りマーロウはかつて、象牙交易で絶大な権力を握る人物クルツを救出するため、アフリカの奥地へ河を遡る旅に出た。募るクルツへの興味、森に潜む黒人たちとの遭遇、底知れぬ力を秘め沈黙する密林。ついに対面したクルツの最期の言葉と、そこでマーロウが発見した真実とは。
著者等紹介
コンラッド,ジョゼフ[コンラッド,ジョゼフ][Conrad,Joseph]
1857‐1924。ロシア占領下のポーランドで没落貴族の家に生まれる。父が独立運動に関与したため一家は流刑、両親を早くに亡くす。16歳で船乗りをめざし、仏英の商船で世界各地を航海する。このときの見聞が、後の創作活動に大きな影響を及ぼす。ポーランド語、フランス語を操り、小説は英語で書いた。1886年イギリスに帰化。1895年『オルメイヤーの阿房宮』で文壇にデビュー。1924年心臓発作のため自宅にて死去
黒原敏行[クロハラトシユキ]
1957年生まれ。英米文学翻訳家(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
Tsuno本棚
-

- 電子書籍
- 【単話版】ド田舎の迫害令嬢は王都のエリ…