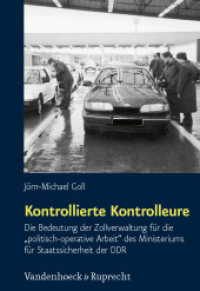内容説明
十七世紀、三十年戦争下のドイツ。軍隊に従って幌車を引きながら、戦場で抜け目なく生計を立てる女商人アンナ。度胸と愛嬌で戦争を生きぬく母の賢さ、強さ、そして愚かさを生き生きと描いた、劇作家ブレヒトの代表作を待望の新訳で贈る。母アンナはこんなにも魅力的だった。
著者等紹介
ブレヒト,ベルトルト[ブレヒト,ベルトルト][Brecht,Bertolt]
1898‐1956。ドイツの劇作家、詩人、演出家。南ドイツ生まれ。1917年ミュンヘン大学哲学部に入学したのち、医学部に転部。’18年に第一次世界大戦に召集され衛生兵として勤務。’22年ミュンヘンで初演の『夜打つ太鼓』が成功をおさめ、一躍脚光を浴びる。ナチスの弾圧を逃れ、’33年から北欧、アメリカと亡命生活を続ける。戦後は東ドイツに戻り、劇団を設立。自らの演劇活動を再開させたが’56年心筋梗塞のため死去
谷川道子[タニガワミチコ]
東京外国語大学教授。ブレヒトやハイナー・ミュラー、ピナ・バウシュを中心としたドイツ現代演劇が専門(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
molysk
56
17世紀、カトリックとプロテスタントが血みどろの争いを繰り広げた、三十年戦争。焦土と化したドイツで、転戦する軍隊を追って物を売る、女商人アンナ。兵士相手の丁々発止のやり取りを、度胸と愛嬌で切り抜ける。アンナが自分の命を危険にさらしながら、それでも守りたいもの。それは、自分の子どもたちだった。だが戦争の惨禍は、ひとり、またひとりと、アンナから愛する子どもを奪っていった――。戦争という泥のなかで、子どもたちを守るためと信じて、軍隊に従って自らも泥にまみれていった母アンナは、聖女も娼婦も超えた存在になった。2022/11/26
Nobuko Hashimoto
17
先日読んだ『編集者の読書論』で知って。舞台は30年戦争時代、父親の違う3人の子を連れて、従軍商人として幌車一つを引きながら欧州中を回る「度胸アンナ」の物語。勇敢な息子を軍隊に、正直な息子も軍の会計係にとられ、幼少期のトラウマで口がきけなくなった娘と2人になる。娘や、知り合った従軍牧師や軍隊の料理人、娼婦らと助け合いながら戦乱の世をなんとか生き抜こうとするが…ナチから逃れて亡命生活を送りながら創作活動を諦めなかったブレヒトの戦争への皮肉が効いている。なお、これまでの邦題は『肝っ玉おっ母とその子どもたち』。2024/07/31
fseigojp
17
30年戦争のことを勉強する傍ら読了 たくましいオッカサンだった 1648年、ウエストファリア条約で近代ヨーロッパが始まったが、戦場であったドイツは領邦国家のままになり1871年にやっと統一(ちなみにイタリアは1860年、日本は1868年) 健全な市民社会の形成が遅れたことがファシズムにつながった2015/08/06
1.3manen
7
1939年初出。解説によると、世界恐慌の頃、経済学や社会学を学んだという(187ページ)。従軍牧師曰く、「私が言いたいのは、平和は戦争の中にあり、戦争も平和だ、ってことです」(109ページ)。違和感がある。平和が戦争にあるという指摘は、平和にも戦争にも線引きはないという、人間の総合性にあるのか。ブレヒトという劇作家は、台詞から訴えかけられるストレートなことばが醍醐味に思えるが、社会科学の知識も台詞に活かされているのは、多くの読者に影響力をもつのだろうと思える。2013/02/17
qwer0987
5
行商人のアンナは戦争を利用して生計を立てている。商売上手だからそれなりに稼いでいるけれど、戦争を利用しながらもその戦争に子どもたちを奪われることには賛同せず、悲憤を感じている。しかし彼女の思惑通りにはいかず、子供たちは全員戦争で命を落としてしまう。悲惨な話だ。でもだからと言ってその戦争で稼ぐという自分の生活を変えることができず、そのように生きていかざるをえないのが、アンナの愚かしく悲しいところだろう。そんな状況を叙事的に感傷をなるべく排除して描いており、じんわりとした哀しみがにじみ出ていて心に残った2018/12/25
-
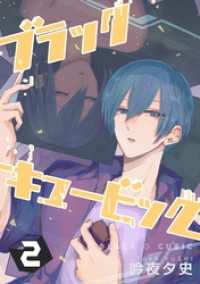
- 電子書籍
- ブラックキュービック(2)
-
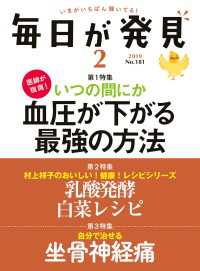
- 電子書籍
- 毎日が発見 2019年2月号 毎日が発見