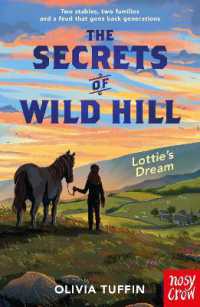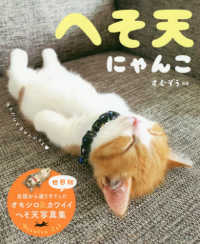内容説明
人間には戦争せざるをえない攻撃衝動があるのではないかというアインシュタインの問いに答えた表題の書簡と、自己破壊的な衝動を分析した「喪とメランコリー」、そして自我、超自我、エスの三つの審級で構成した局所論から新しい欲動論を展開する『精神分析入門・続』の2講義ほかを収録。
目次
人はなぜ戦争をするのか
戦争と死に関する時評
喪とメランコリー
心的な人格の解明
不安と欲動の生
著者等紹介
フロイト,ジークムント[フロイト,ジークムント][Freud,Sigmund]
1856‐1939。東欧のモラビアに生まれる。幼くしてウィーンに移住。開業医として神経症の治療から始め、人間の心にある無意識や幼児の性欲などを発見、精神分析の理論を構築した。1938年、ナチスの迫害を逃れ、ロンドンに亡命。’39年、癌のため死去
中山元[ナカヤマゲン]
1949年生まれ。哲学者、翻訳家(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
藤月はな(灯れ松明の火)
77
表題作は『博士の異常な愛情 または私は如何にして心配するのを止めて水爆を愛するようになったのか』を観た時、次々と起こる原爆が落っこちそうな事態の発生やまだ、起こる紛争に対し、その状態を食い止めようとしつつも結局はタナトスに突き進むかのような行動を取ってしまう周囲を思い出しました。一番、納得してしまったのは「喪とメランコリー(鬱病)」。鬱病が実は自分を罰しつつもそうなるきっかけを生み出した環境や人物(親など)を糾弾するという、サディスティックな自慰的行為という指摘はそうなりそうな私にとっては言えて妙でした。2015/05/21
かわうそ
41
面白い。ショーペンハウアーとフロイトの違いはショーペンハウアーは死のみを求めるのだが、フロイトは生も死も平等に容認するということだろう。 破壊的欲動(タナトス)を統一的欲動(エロス)で文化的な方向に修正する必要がある。人間が本来は破壊的欲動を有することは、生物がそもそも無機物からなること(無機物に戻そうとする欲求)から明らかだと彼は言います。 彼は軽く流してますが私は理念が権力に屈するのが世の常だから理念を追い求めるべきではないと考えることはナンセンスだと思う。逆に理念がないからこそ権力が暴走するといえる2024/11/15
かわうそ
41
フロイトは人間には破壊的欲動と統一的欲動の2つの相反した欲動が備わっていると言います。後者の統一的欲動とはプラトンが『饗宴』で持ち出したエロスに他なりません。カントはこれを『社交性』と表現しました。人間の破壊的欲動にエロス的欲動が加えられることで、社会的欲動が形成されるのです。 なぜ現代は自殺という行為が増えてしまったのか。 『他方で純粋に心理学的に考察してみれば、自我はみずからの欲求を社会のために犠牲にしたのであり、攻撃欲動の破壊的な傾向を抑圧しなければならなかったのですから、自我は社会において居心地2023/08/26
香取奈保佐
41
乳首を噛む赤ちゃんの行動から、人間が抱く欲の構造へと話が広がる。何かを「愛でたい」と思うとき、そこに「攻撃したい」という感情も芽生える――■予備知識なく、初めてフロイトの著作に体当たり。発想の断片を拾い集め、とても論旨を味わえたとは言い難い■しかし、「どうやって思いついたのか」という論が散見され、面白かった。「トンデモ理論」と紙一重というイメージがあったが、天才なのだろう■自我が、外界と超自我、エスの間を取り持っている。躁と鬱など様々な症状も、「ひとりの人間の中に対立がある」と考えると確かに分かりやすい。2021/04/18
かわうそ
35
原始人は好んで人を殺すというのは嘘だろう。それが初期の定住生活者のことを原始人と表現しているのならばそれは正解になる。というのも狩猟生活において住むところというのはあまり拘らないのであって抗争になる前にどちらかのグループが必ず退くからである。争いが耐えなくなったのはあくまでも定住生活がはじまりその土地を耕したりすることによってその土地に価値が出てきた時からである。なぜなら定住生活をしていればなかなかそこから退かないのだから争いになるのは当然の帰結となる。2022/03/30
-

- 電子書籍
- 悪役令嬢、ブラコンにジョブチェンジしま…
-
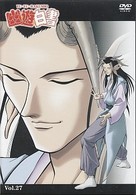
- DVD
- 幽☆遊☆白書 Vol.27