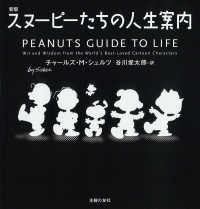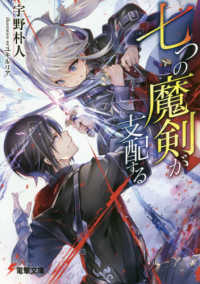内容説明
乗客が降り去り、がらんとした車内で、「ああ、こうやって、私も年をとっていくのか」とつぶやく(「バスに乗って」)。花々に囲まれ、「怖くなり、こうしたときは、人としての身分を捨てて、花の一族にそっと加わったら、楽しかろう」と感じる(「真夜中の花と不思議な時間」)。日常の何気ない情景を、繊細でありながらも力強い筆致で、見事なまで清新に描き出すエッセイ集。
目次
バスに乗って
言葉のない世界
カフェの開店準備
カミサマの居る場所
しんとぼん
小名木川
岸上さんの誕生日
潮風の思念
蟹を食べる
書庫と盗作〔ほか〕
著者等紹介
小池昌代[コイケマサヨ]
1959年東京・深川生まれ。津田塾大学国際関係学科卒業。詩人であり小説家。’97年『永遠に来ないバス』で現代詩花椿賞、2000年『もっとも官能的な部屋』で高見順賞、’01年『屋上への誘惑』で講談社エッセイ賞、’07年「タタド」で川端康成文学賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
UK
29
独特。うーんこんな文体は珍しい。ちょっと新鮮な詩人のエッセイ集。おんなであることを当たり前に肯定して柔らかく自然な好奇の視線を瞠っている。視覚・触覚・聴覚がつかんだものをくるりっとまわしてふわっと、でもしたたかに差し出してくる。この人の描写には味覚と嗅覚がほとんど出てこない。さ行の透明感があって、ま行のやわからい腰が文章を支える。ひらがなの感覚を大事にした使い方がすごく印象的。2014/09/11
アキ・ラメーテ@家捨亭半為飯
26
1994~2001年までに、あちこちで書かれたものを集めたエッセイ集。10年以上前のものなのに全く古びない。日常について書いたものでも、過去の出来事につて書いたものでも、詩につて書いたものでも、どれも言葉が選び抜かれている印象。読んでいる方はスラスラ読めるけれど、ものすごく丁寧に書かれたものではないかという印象を受ける。「チェンバロの夜」と「母の怒り」がすばらしい。言葉にならない小さなため息……。2015/02/01
kaoriction@本読み&感想 復活の途上
25
エッセイ集でこんなにザワザワしたのは初めてだ。何だろう、このザワザワ感は。日常の何気ない情景であるのに、緩やかに、じんわりと、連れて行かれるその世界。あまりにも日常的なことなのに、異次元のような。観念的だな、と思う。詩人ならではの繊細な描写、情景、背景。語り口も柔らかで当たりが良いのに、着地点はどこか観念的だ。いつもは軽い気持ちで読むことの多いエッセイ集だが、この作品は、眉間にシワ。情景描写には川の町で育ったことが伺えるような「流れ」を感じる。「バスに乗って」「カフェの開店準備」「人殺し」が興味深く好き。2014/08/21
tom
9
ハードカバーは、岩波書店から出版というのが面白い。さすがに詩人の文章。言葉に対する感覚が違うなあという読後感。たとえば「日常生活というものは、なにげない顔をしているが、峻烈なものである。それはたとえば、しばらくほったらかしにしておいた換気扇の、あの逞しい汚れが象徴している。汚れ---そうだ。家族の恥ずかしさは、あの汚れのようなものと、関係があるのかもしれない。」なんて文章、というてい私の脳内に現れることはない。でも、読後には、家族の恥ずかしさが換気扇の汚れとシンクロしてしまう。だからこの人の文章は面白い。2014/08/24
つーさま
6
どのページを開いてもそこに現れる光景は、普段私たちが生活する中で目にするようなありふれたものばかりだ。けれどもどこか決定的に違っている。そこに流れる空気は新鮮で、どことなく美しいのだ。もちろんそんな光景を目にした際に沸き起こったざわめきを忘れずちゃんと書きつけている。本書はエッセイの体裁を取っているものの、中身そのものはどれも立派な詩だ。そう、小池昌代は詩人なのだ。詩人が何かを感じ書く時、それはいつしか詩へと姿を変えてしまう。この本はその瞬間をまざまざと見せつける。(続)2013/05/10
-

- 電子書籍
- 今日から先輩を忘れます(6) バニラブ