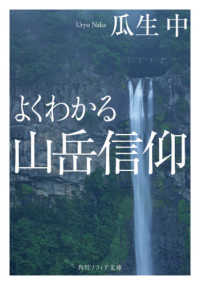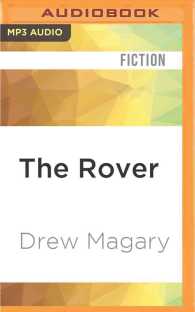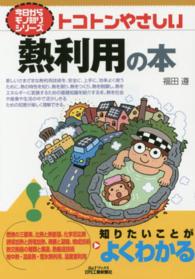出版社内容情報
狩猟採集生活→農耕革命→生産増→人口増→貧富の差→都市→国家という、我々の多くが信じてきた「進歩史観」は正しいのか? 人類学者デヴィッド・グレーバーと考古学者デヴィッド・ウェングロウの共著『万物の黎明』は、この進歩史観をくつがえし、世界中に衝撃を与えた。本書は『万物の黎明』に大なり小なり衝撃を受けた日本の考古学者が集い、自らの最新研究を基に、人類史のパラダイムシフトを行う試みである。
【目次】
内容説明
狩猟採集生活→農耕革命→生産増→人口増→貧富の差の出現→都市の誕生→国家の誕生という、我々の多くが信じてきた「進歩史観」は正しいのか?人類学者デヴィッド・グレーバーと考古学者デヴィッド・ウェングロウの共著『万物の黎明』は、この進歩史観をくつがえし、世界中に衝撃を与えた。本書は『万物の黎明』に大なり小なり衝撃を受けた日本の考古学者が集い、自らの最新研究を基に、人類史のパラダイムシフトを行う試みである。
目次
序章 もうひとつの〈文明〉論、あるいは〈科学〉としての考古学
第1章 インダス〈文明〉論
第2章 『万物の黎明』への共鳴と、どこしれずすれ違いを感じる自分―南米アンデス文明を例に
第3章 モニュメントの造営と社会―日本列島の古墳時代を考える
第4章 オセアニア研究から見た『万物の黎明』―グレーバーとサーリンズ
第5章 国土なき国家、王なき帝国―古代イラン、先アケメネス朝期の知られざる社会
第6章 まじめな農耕のはじまり
第7章 狩猟採集民とモニュメント
第8章 エジプト初期王権の受容・広域化と死者・祖先へのケア
第9章 ディルムンとマガン―『万物の黎明』から見たペルシア湾岸の古代文明
第10章 モノとヒトの絡み合いとしての交易―メラネシアの交易システム「クラ」を中心に
第11章 都市と市場および貨幣の問題
第12章 『万物の黎明』まで―その形成のプロセスを二人のテキストでたどる
著者等紹介
小茄子川歩[コナスカワアユム]
京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科特任准教授。専攻は南アジア考古学、比較考古学。2008年度インド政府招聘留学生としてインド・プネーに留学以来、インダス文明社会のあり方を人類史に正しく位置づけるべく日々奮闘中。〈文明〉とは何か、を問い続けている。著書『インダス文明の社会構造と都市の原理』(同成社)で、第六回日本南アジア学会賞受賞
関雄二[セキユウジ]
国立民族学博物館館長。専攻はアンデス考古学、文化人類学。1979年以来、南米ペルー北高地において神殿の発掘調査を行い、アンデス文明の成立と変容を追究するかたわら、文化遺産の保全と開発の問題にも取り組む。2008年度濱田青陵賞受賞、’15年ペルー文化功労者、’16年外務大臣表彰、’23年ペルー大功労勲章受章(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
佐倉
チェアー
がんちゃん
Hayato Shimabukuro
黒胡麻