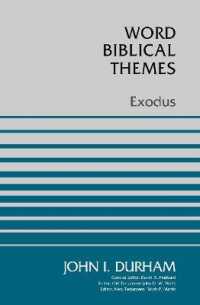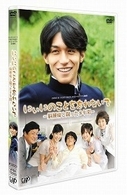出版社内容情報
世の中の発達とともに失われていった身体技法は、疫学研究者である著者の興味をひいてやまない。ある身体技法ができる、ということはどういうことか。なぜできるようになるのか、なぜできなくなるのか。本書では今はこの国でほとんど失われてしまった身体技法「頭上運搬」の記憶を追う。沖縄や伊豆諸島をはじめ日本各地や海外にその痕跡を訪ねつつ、話題は着物や伝統衣装、お産のほか、生活と労働を支えていた身体技法へと広がる。
内容説明
今の日本では、ほぼ失われつつある身体技法「頭上運搬」。かつては日本各地で行なわれており、高齢の方の中にはその記憶をとどめている人もいる。経験した方は、「誰でもできた」「やろうと思えばできる」と言う。しかし、他の身体技法や知恵と呼ばれるものと同様、その経験が三世代も途切れると、後の世代には想像もつかないものとなる。ある身体技法ができる、ということはどういうことか。なぜできるようになるのか、なぜできなくなるのか。それをしていた頃としなくなってからの、自らの身体への理解や意識に差はあるのか。本書では、沖縄や伊豆諸島をはじめ日本各地や海外に頭上運搬の記憶と痕跡を訪ねる。話題は生活と労働を支えていた身体技法へと広がる。
目次
1 失われゆく身体技法(三世代―知恵は見事に消える;「意識」する;アフリカ研究者たち ほか)
2 頭上運搬の記憶をたずねて(昔々あるところに…;箱枕とインボンジリ;ついぼ ほか)
3 生活と労働を支えた身体性(「センター」は体のどこに?―頭上運搬の美しさの秘密;生活を支える身体の使い方、生活を支える運動;敬意と頭上運搬―高く、美しく運ぶやり方 ほか)
著者等紹介
三砂ちづる[ミサゴチズル]
1958年山口県生まれ。兵庫県西宮市で育つ。京都薬科大学、神戸大学経済学部(第二課程)卒業、琉球大学大学院保健学研究科修士課程修了。’99年ロンドン大学PhD(疫学)。ロンドン大学衛生熱帯医学院研究員、JICA疫学専門家として疫学研究、国際協力活動に携わる。ブラジルで約10年間暮らした後、帰国。2001年より国立公衆衛生院(現・国立保健医療科学院)疫学部に勤務。’04年より津田塾大学学芸学部教授。’24年3月に退職し、八重山で女性民俗文化研究所主宰。ゆる体操正指導員。運動科学総合研究所特別研究員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- DVD
- 修羅の荒野3 迷い道