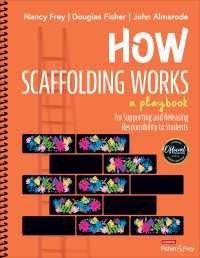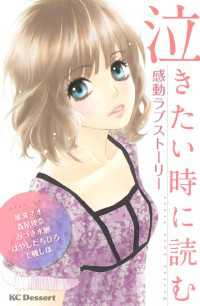目次
序論 教会とアメリカ合衆国
第1章 植民地の教会(ヴァージニア植民地;プリマス植民地 ほか)
第2章 アメリカ合衆国の独立へ(なぜ教会の歴史なのか;ニューイングランドの会衆派 ほか)
第3章 南北戦争からアメリカ帝国へ(南北戦争のころ;地理的拡大と宗教の変容 ほか)
第4章 キリスト教と現代アメリカ(戦後とキリスト教;公民権運動 ほか)
著者等紹介
橋爪大三郎[ハシズメダイサブロウ]
社会学者。大学院大学至善館教授。東京工業大学名誉教授。1948年神奈川県生まれ。1977年、東京大学大学院社会学研究科博士課程単位取得退学。執筆活動を経て、1995年~2013年、東京工業大学教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
trazom
104
本書は「ケンブリッジ版・アメリカの宗教の歴史」(全三巻)の翻訳が中心。橋爪先生も「私はちゃっかり要約して一冊にまとめたわけだ」とあとがきで白状。主観を排した教科書的な内容だが、アメリカの教会に関する歴史的・地理的な事実関係を知る百科事典として貴重な資料ではある。国と公定教会との関係が明確な欧州諸国と違って、教会同士が自由競争を行うアメリカだからこそ、多様な教派が互いに切磋琢磨する状況が生まれたのだとわかる。今、史上二人目のカトリックの大統領が誕生したが、私には、その人が人工妊娠中絶を容認するのが不思議…。2022/12/28
榊原 香織
71
アメリカを理解するにはキリスト教知識が必要 でもちょっと読みずらかった。 参考文献を抜き書きして翻訳、羅列してるので。 歴史、宗派も複雑だし。でも流れはわかった。キリスト教系新宗教、カルトにも触れている2023/01/13
ネギっ子gen
51
【教会がアメリカをつくった】『教養としての聖書』などの著書で知られる社会学者が、アメリカのキリスト教と教会について解説した新書。巻末に参考文献。写真多数。コラムで「さまざまな教会・宗派」を紹介。『ケンブリッジ版・アメリカの宗教の歴史』(全3巻)に依拠。<日本人のアメリカ理解は、えてして表面的である。アメリカにそれなりに詳しいひとでも、似たようなものだ。なぜか。それはアメリカの教会を、すっ飛ばしているからである。日本人は、キリスト教の理解が足りない。アメリカの教会の歴史をわかっている人は、なお少ない>と。⇒2024/03/22
軍縮地球市民shinshin
13
著者は小室直樹に師事した社会学者なのだが、師匠と違ってサヨクなので今まで著作を読んだことはなかった。テーマが面白そうなので発売時に買っていて、積ん読になっていたのを今回読んでみた。アメリカで出版された『アメリカの宗教の歴史』全3巻を中心として要約したもの。文章は師匠の小室を意識したのかやたらと改行ばかりしているのが印象的だが、小室ほどインパクトのある文章ではない。橋爪の社会学の専門はなんだか知らないのだが、本の要約なのでどうもわかりにくいところが多々あった。ただまとめると、アメリカはキリスト教の国だが独立2024/03/23
sawa
7
★★★★☆ アメリカのキリスト教の様々な宗派の歴史を入植時代から、テレビ伝導師まで、時代を追って解説する本です。 これまでルーツによってカトリックとプロテスタントに分かれてて、変わった宗派もいくつかあるようだという位の浅い認識だったので、目から鱗がボロボロでした。 まず歴史の話として面白い。イギリスからの入植者には英国国教会の信者も多かったのになぜ衰退したか、アフリカから連れて来られた黒人達がなぜキリスト教信者になったかなど。(コメントへ続く)2023/01/07