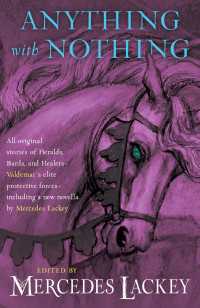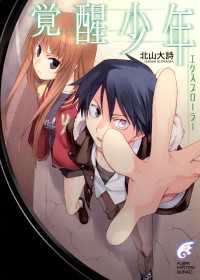出版社内容情報
大学の意義が見失われ、外面が取り繕われた「役に立ちそうな」研究ばかりが生き残る現状が日本の知的な生産力を低下させている。
目次
序章 「大学とは何なのか」が問われた2020年
第1章 私が経験した大学の野蛮さ
第2章 教員として教えた野蛮な作法
第3章 研究者は荒野を目指す
第4章 野蛮に生きるには教養が不可欠である
第5章 大学を野性と理性の「動物園」にせよ
著者等紹介
酒井敏[サカイサトシ]
1957年、静岡県生まれ。京都大学大学院人間・環境学研究科教授。2021年4月からは静岡県立大学副学長を兼任。1980年、京都大学理学部を卒業。1981年、同大学院理学研究科修士課程中退後に助手として採用され、以来同大学一筋に40年在籍。専門は地球流体力学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
gonta19
129
2021/10/23 メトロ書店御影クラッセ店にて購入。 2022/2/1〜2/2 「京大変人講座」を立ち上げた酒井敏先生の大学論。いや、全くおっしゃる通り、という内容。本当にこのまま大学を縛り付けていると、日本の国力はどんどん低下、大学生も損、大学教員も損、会社も損、ひいては社会全体が損という四方全損状態になってしまう。2022/02/02
海燕
13
大学が野蛮になったと嘆くのではなく、大学たるところ、野蛮であるべきだというのが京大で長く教えた著者の主張。大学の研究や教育は未開の地を手探りで切り拓いて進んでいくもの、との思いが「野蛮」のワードに込められている。はじめから進路が見通せている洗練されたものではない。そして、未開の地を行くにも、動物のように本能を持たない人間が野性の勘だけに頼るのは危険であり、それを回避するための能力が理性や知性。教養はそのベースとなるもの。教養教育を疎かにする方向に向かった大学改革に対する、異議の申し立てでもある。2024/12/09
山のトンネル
5
類書『「役に立たない」科学が役に立つ』2021/11/11
Yappy!
4
最近種々玉石混交などなど、いろんな大学論が溢れていますが、これは大学論という名のもとこの教授が考える大学の在り方についての意見集でしょうか。じっくり大学人と話をすれば多かれ少なかれ似たような話を聞くでしょうし、こうした話をする人とじっくり何かすることは、とてつもなく楽しい時間になる。 野蛮なという言い方で凝り固まった偏った大学へのまなざしを、少し自由に、面白く、そして暗い業界を少し前向きに考えることができます。おもたーい大学論を読む間の息抜きとして、そして近場にこういった人を探してお話のきっかけに。2021/12/26
乱読家 護る会支持!
2
大学生の時にはほとんど勉強しなかった僕ですが(笑)、社会人になってから「自分の能力」の低さに直面する場面が多く、いろいろと勉強しました。特に大学の先生のお話を真剣に聞く機会は、大学生時代よりも社会人になってからの方が多かったと思います。 今は、人生100年時代で情報があふれる時代。それだからこと、「確かな知識」を求めるニーズは高まっていると思います。 「確かな知識」を得られる場として、今以上に「開かれた大学」になることを望みます。2024/11/06