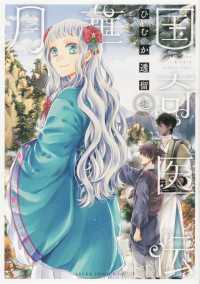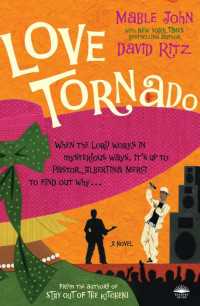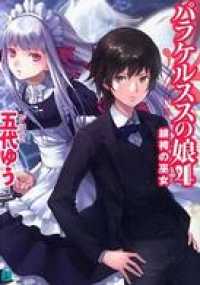出版社内容情報
外国人に依存するニッポンの現状を、公表されたデータから分析し全国各地を取材。移民国家となりつつある日本のこれからを考える。
内容説明
改正出入国管理法が2019年4月から施行され、外国人の受け入れ拡大が進む日本。だが、現実は私たちの想像をはるかに上回る。もはや企業も自治体も、そして日本社会全体も外国人なしでは成り立たないという声が各地で上がっているのだ。職場の戦力として、地域の一員として、言葉の壁やいじめ、孤独や老いに悩む一人の人間としてこの国で生きる彼ら彼女らの、等身大の姿を見つめ直さなければならない。NHKの特設サイト「外国人“依存”ニッポン」取材班がオープンデータを独自に分析し、日本社会で進む外国人への“依存”の実態を明らかにする。
目次
第1章 「労働者」として考える外国人“依存”(外国人がいなければ続けられない;選ばれない国・日本)
第2章 「社会の一員」として考える外国人“依存”(日本人の減少を埋める外国人;超・多国籍化する街 ほか)
第3章 「人生」「家族」として考える外国人“依存”(「誰も知らない」子どもたち;いじめとルーツ ほか)
第4章 「移民国家」の事例から考える外国人“依存”(OECD第2位の増加数;目指すは移民の“統合”―ドイツ ほか)