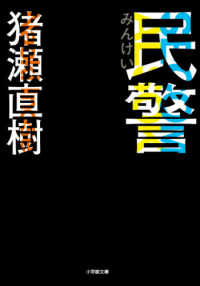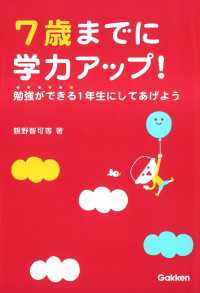出版社内容情報
ロボットアニメ研究の第一人者が、マーチャンダイジング(商品化)の歴史とともに、ビジネスマン向けにロボットアニメ史を解説。
内容説明
第一人者による世界初の論考!ロボットアニメと、その玩具・模型に関する進行形のビジネス史。
目次
序章 1972―ガッチャマンとマジンガーZ
第1章 キャラクター商品とホビーの躍進
第2章 変形・合体とマグネット
第3章 宇宙戦艦ヤマトとバンダイ模型の台頭
第4章 ガンプラ狂騒曲
第5章 ロボットアニメのピーク
第6章 オリジナル変形・合体ロボットと黒船襲来
第7章 ディフォルメロボットの時代
第8章 世代交代と超合金魂
著者等紹介
五十嵐浩司[イガラシコウジ]
1968年青森県生まれ。アニメーション研究家。学生時代からライターの活動を始め、’92年よりフリーのルポライターとして独立する。主なジャンルはアニメーション、特撮と、玩具や模型のホビー関連。’92年に株式会社タルカスに参加し、編集者兼ライターとして、多くの書籍や映像ソフトの解説書を手がける(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
リキヨシオ
20
日本のロボットアニメにとって、1972年は大きな転機になった。この年に放送された「科学忍者隊ガッチャマン」はメカニック描写を変えて「マジンガーZ」は「ロボットアニメーション」というジャンルを確立させた。同時にロボット玩具ビジネスも始まり「超合金」や「ポピニカ」などダイキャスト玩具が人気を博す。本書は1972年から始まったロボットアニメビジネスの進化の歴史を記している。超合金、ガンプラ、トランスフォーマーなどロボット玩具について詳しく述べているが個人的にはそれぞれの写真があればもっと分かりやすいと思った。2018/01/13
シャル
9
日本のロボットアニメとその玩具の関係の歴史を紐解いた一冊。そこまで詳しくないがある程度知っている自分の目から見て、当然知っているもの、名前くらいは聞いたことがあるもの、全く知らないものに別れて、まさに歴史の光と闇といった物を感じる。ガンダムと並んで重要ポイントにトランスフォーマーが上げられており、まえがきにあったガンダムはシリーズごとに機体が変わるがトランスフォーマーはオプティマスとバンブルビーを軸に固定したというのも興味深い。誰に売るか絞ル重要性、さりとて作品人気に振り回されるビジネスの難しさも感じる。2017/09/26
as
8
ミクロマンやロボダッチは雑誌の広告を見るだけでその世界観にワクワクしたものです。ガンプラに関していえば初めて買ったのがジムとコアブースターで、それでも買えただけでも嬉しかったのを覚えています。(次に買えたのが武器セットとアッグガイ)ちなみにGアーマに付いてる1/144のガンダムはABパーツが分離する優れものでした。2017/10/22
Tenouji
8
ゼータ以降のガンダムとか、BB戦士あたりから、全く知らなかったんだが、ようやくつながりと、流れがわかったよ。2017/09/02
pppともろー
4
どんなビジネスにもドラマがある。とても興味深く読んだ。2018/02/25