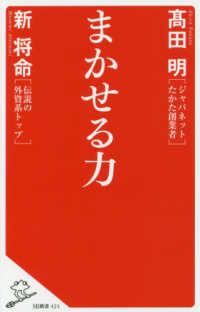内容説明
儲けの構造が読めると、経営がわかる。経営がわかると、日本がとるべき戦略がわかる。それがすべて表れているのが財務諸表である。項目はざっくりまとめて、わからない言葉はとりあえず無視。バランスシート(BS)と損益計算書(PL)の大きさ、利益の3つだけを見ればいい。「ちょうどいい加減にとらえる」ことが、会計リテラシーのカギである。一番の近道は、知っている会社の財務諸表を読むことだ。図で見れば、業界をリードする企業の戦略の差が一目でわかる。リアルな財務諸表をざっくり、たくさん読むということに、本書でチャレンジしてほしい。
目次
はじめに 会計がわからんで経営がわかるか!
第1章 エレクトロニクス・IT業界編
第2章 自動車業界編
第3章 小売業界編
第4章 製薬業界編
第5章 住宅・インフラ業界編
著者等紹介
山根節[ヤマネタカシ]
1973年、早稲田大学政治経済学部卒業。’74年、監査法人サンワ事務所(現トーマツ)入社。’82年、慶應義塾大学大学院経営管理研究科修士課程修了後、コンサルティング会社を設立。2001年から慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授(現名誉教授)。2014年から早稲田大学大学院教授(ビジネススクール)。商学博士。専門は、会計管理、経営戦略、マネジメント・コントロール(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。