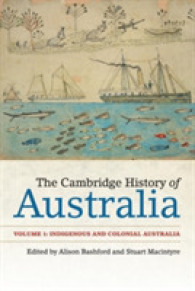内容説明
2009年春から毎月のように勃発する抗議デモ、抵抗運動の意味するところは?激変する中国の現在を活写した、渾身のルポ。
目次
問題は「反日」ではなく、「親日」の不在
第1部 「反日」から目をそむけては、今の中国は読めない(党からはみ出した「ごく普通の中国人」;民間運動としての「反日」;消された声)
第2部 北京郊外に渦巻く民間(官方と辺縁;官方に対する市民感覚)
第3部 2つの民間と党(自由と権利を主張する人たち;社会主義と愛国;党を超える行動主体)
親中・反中を超えて
著者等紹介
麻生晴一郎[アソウセイイチロウ]
1966年福岡県生まれ。大分、神奈川で育つ。東京大学国文科在学中の’87年から上海、ハルビンなどを放浪。大学卒業後、テレビマンユニオンに就職するものの3年足らずで退社。以来’98年までの大半を中国、香港、タイ、ラオス、インドや東京の中国人社会などで過ごし、無一文同然の生活を送る。’98年より執筆とテレビ制作開始、2003年より執筆に一本化(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ラウリスタ~
8
もう10年近く前の本で、GDPが逆転された今とは当然違いがあるだろうが、お上(中国共産党)のやることを嘘っぱちだと冷めた目で見る民間(必ずしも虐げられる弱者というイメージには重ならない)に焦点を当てた本書はいまでも十分に読まれる価値はあるだろう。反日を政府のプロパガンダに洗脳と片付けてはならない(政府を嫌う人たちは、自分がネットで真実を知ったと語りたがる)。また政府批判を全て、欧米的な「自由を求める活動家」として十把一絡げにも出来ない。地方政府の腐敗ぶりは目を覆うものがある、これは上からの改革で変わったか2018/05/27
西澤 隆
5
中国は一党支配だから日本にもたらされる「中共に刃向かう市民」的な情報やネット経由の話しも視点は結局政府側からの「大きな物語」として語られる。誰でも見られる場所に情報を置くことがリスキーだからこそ人と会ってそのつながりでちいさな状況を丁寧に見ていこうという著者のスタイルはなるほどと思うし大きな国では数多くの統一的じゃないちいさな動きがたくさんあるのだなとあらためて思う。政治が全てを制御しようと試みることのいろんな影響は、こんな感じで出るのか。サッカーアジア杯での暴動の見方も読了するとずいぶんかわってきました2018/01/05
Yasutaka Nishimoto
2
著者の立位置からすると、もっと書きたいこともあるだろうが、私たちが中国情勢に感じる素朴な疑問、違和感に対して、ある一定の見方、取り組み方を示してくれる。その中で、これから中国という大きな枠組みが、これからどこに向かっていくのかという、想像するしかないことについても、一定の考え方を提示してくれている。2016/06/17
久恒啓一
1
先日会った麻生晴一郎さんは、どこに住んでいるんですかという私の問いに、ごく自然に「東アジアに住んでいます」と答えた。体制からはみ出しているアーチスト、サークルやサロンで語り合う人々、ロック村の様子、人権弁護士の活躍、四川大地震で登場したボランティア、農村を作りかえようとするNGOなど市民とでも呼ぶべき人々が様々なテーマで台頭している。全体をつかもうとする目ではなく、ミクロの動きに身を投じ、それを丁寧に積み重ねていこうという方法論。「反日」の本当のメッセージは「民を見つめろ」だ、という彼の指摘には納得した。2014/10/02
Hiroko
1
著者と知り合ってからの再読。だからこそ、お酒を飲みながら中国での見聞を拝聴しているような感じ。実際の中国が肌で伝わってくる。2014/06/25