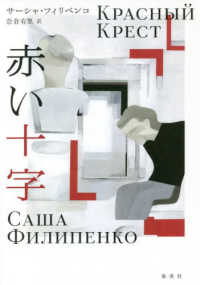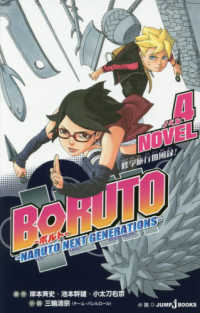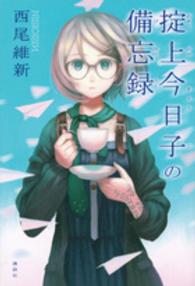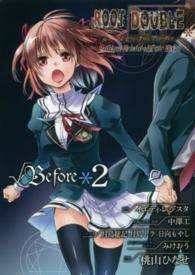出版社内容情報
ものづくりで培った知が、サービス・流通業に、アジアから中東、豪州に拡がっている。現場からの最新報告。
内容説明
産業の構造変化、国際化に対応するものづくり戦略とはどういうものか?実践・研究の第一人者たちが、ものづくり学の可能性を描き出す。
目次
第1部 ものづくり経営学総論(統合型ものづくり戦略論;アーキテクチャのポジショニング戦略 ほか)
第2部 ものづくり経営学各論(設計情報から見たものづくり;階層的ものづくり競争力論―日本自動車産業はなぜ強いか ほか)
第3部 非製造業のものづくり(サービス業に応用されるものづくり経営学;トヨタ生産方式の販売業への活用 ほか)
第4部 アジアのものづくり(アジアものづくりの比較優位説;韓国自動車ものづくりと組織能力 ほか)
著者等紹介
藤本隆宏[フジモトタカヒロ]
1955年、東京都生まれ。東京大学経済学部卒業。三菱総合研究所を経て、ハーバード大学ビジネススクール博士課程修了(D.B.A.)。現在、東京大学大学院経済学研究科教授兼ものづくり経営研究センター長、独立行政法人経済産業研究所(RIETI)ファカルティフェロー、ならびにハーバード大学ビジネススクール上級研究員。専攻は、技術管理論・生産管理論・経営管理論(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
61
ものづくりの観点から見た経営学書です。新書の割には内容が本格的で普通の版にして教科書としてもよかったのではないかと思われます。第1部では総論、第2部では各論、第3部では非製造業、第4部ではアジアとくに韓国、中国における自動車産業について焦点を当てています。トヨタ生産方式に対してホンダウェイ、販売業へのトヨタ生産方式の適用などが私の興味をひきました。2015/07/29
sabosashi
6
端的にいえば製造業の経営学が詳述されているわけで、わたしが読む本としては異色。 しかしたとえばメキシコにおいては、製造業よりもモノを動かして利益を得る、という傾向があり、エンジニアよりもマネージャーのほうにより脚光があたる。 エンジニアが経営者に登りつめることもあるニホンとは好対照。 さて戦後、急発展をとげたニホンの工業を中心とした産業は、80年代から90年代にかけて凋落の憂き目をみる。 2016/12/08
りょう
6
トヨタ生産方式をベースに、主に製造業について多くの学者が語りまくる500ページ超の読者層のよくわからない新書。サブタイトルが生産方法や理論ではなく、生産”思想”としているのは、その思想が、販売業やスーパーマーケットの運営、はたまた病院運営にも取り入れられていることから、さもありなん、という感じ。中国の製造業の章での、疑似オープン・アーキテクチャと創造的リバースエンジニアリングのところが面白かった。2007年出版なので、数年後だけれども劇的に変わった現代についても、著者たちに語ってもらいたい。2013/12/18
富士さん
4
映像産業を製造業として位置づけるために使えないかと再読。はじめて読んだ時以上に使える印象でした。いろいろと勉強した後に改めて見る四象限はよく考えられていると思います。そして、昔の自分と思ったことがあまり変わっていない・・・。2023/10/15
たか
3
製品を「設計情報が媒体に転写されたもの」と定義し、その観点から組織能力やワークフローを考察する。インテグラル(擦り合せ)↔モジュラーの二項対立を、内部↔外部(市場)それぞれの目線からみたマトリクス分類がわかりやすい。(著者は違うと言っているが)日本での影響力が強すぎて殆どトヨタ生産方式の話であるような印象が残る。地政学的分類は最初疑わしく思ったが、雇用慣行が多能工化など企業の育成方針に影響し、それが組織能力として表出するのは納得。表面だけ見た追随は逆効果、強みを発揮できるポジショニングを考える必要がある。2024/11/09