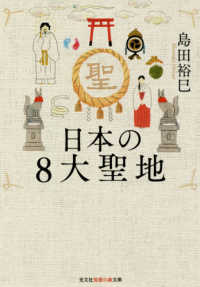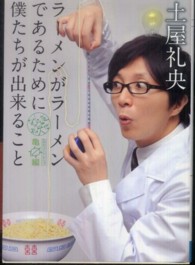内容説明
著者は、論理的思考の研究と教育に、多少は関わってきた人間である。その著者が、なぜ論理的思考にこんな憎まれ口ばかりきくのかといえば、それが、論者間の人間関係を考慮の埒外において成立しているように見えるからである。あるいは(結局は同じことなのであるが)、対等の人間関係というものを前提として成り立っているように思えるからである。だが、われわれが議論するほとんどの場において、われわれと相手と人間関係は対等ではない。われわれは大抵の場合、偏った力関係の中で議論する。そうした議論においては、真空状態で純粋培養された論理的思考力は十分には機能しない。
目次
序章 論理的思考批判
第1章 言葉で何かを表現することは詭弁である
第2章 正しい根拠が多すぎてはいけない
第3章 詭弁とは、自分に反対する意見のこと
第4章 人と論とは別ではない
第5章 問いは、どんなに偏っていてもかまわない
著者等紹介
香西秀信[コウザイヒデノブ]
昭和33年香川県生まれ。筑波大学第1学群人文学類卒。同大学院博士課程教育学研究科単位修了。琉球大学助手を経て、宇都宮大学教育学部教授。専攻は修辞学(レトリック)と国語科教育学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
HMax
38
この本をマスターした人と議論したら、怒り狂ってしまうこと確実。「議論に世の中を変える力はない。何かを変えたいのなら、裏の根回しで数工作したほうが確実。論理的思考力や議論の能力など弱者の護身術。強者には要らない。議論のルールなど、弱者の甘え以外の何ものでもない。」。どしどし使うと決めたのが、①論点のすり替え、②定義を確認する、③定義を聞かれれば、あなたと同じようなものですと答える、④ 質問にイエスかノーで答えず質問の意味を問い返す。 とは言っても頭が良くないと、すぐに切り返すことが難しい。2024/10/09
かんらんしゃ🎡
38
都知事選以来石丸構文が話題で、かみ合わない討論は多分意識してやってるんだろうな。もう少し知りたくて、アタリを付けてこの本借りて来た。質問に質問で返す、論点ずらす、定義を問われてもとぼける、まさに石丸伸二。議論討論には使えるメソッドは何でも使えと書いてある。相手に忖度せずとにかくマウント取れば勝ちみたいな、なかなか意地の悪い本であった。2024/08/06
チェリ
12
いやあ、面白いです。最初から「論理的思考力や議論の能力など、所詮は弱者の当てにならない護身術である。強者には、そんなものは要らない。いわゆる議論のルールなど、弱者の甘え以外の何ものでもない。」とぶっ飛ばし気味に始まり、そのまま失速せずに駆け抜けていきました。また「冷蔵庫にビールがない」というのは事実ではあるけれど、それを言うこと自体「ビールがあると期待(予測)」していた意見でもあるという、事実があえて言及されることで意見に変わるという視点が面白い。「論点をすり替えて何が悪い」の章もかなり刺さった。2023/09/23
えんど
11
議論や文書を「きちんと」やろうとすると論理学を勉強して前提!論拠!とかやるけど現実は論理にそってない議論が多いしそれが論理的に間違ってても間違いではないことけっこうあるよねと「論理的」な説明で面白かった。2019/11/26
佐藤嘉洋
11
議論というのは難しい。 相手を理解するためでなく、論破しようとする人は、何を目的としているのだろう。 おそらく「論破した自分が気持ち良い」だけで、「周りには恨みしか残らない」のではないだろうか。 「論破してやったぜ」と得意気に語る人にはなりたくない。 私は、相手の考えを聞き、さらに自分の考えも聞いてもらい、互いの妥協点を探したい。 けっして喧嘩をしたいわけではない。 お互いにとってよりよい状態を目指したいから話し合いたいのだ。 そうでないなら時間の無駄だ。 そんな人とは話もしたくないのが本音だから。2016/02/07