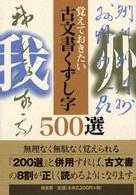内容説明
「カネ余りの不況」世界史上稀な現象がなぜ日本で起きたのか?「マクロの論客」明日への直言。
目次
第1章 オーバーバンキング―預金は余っている
第2章 長引く不良債権問題―なぜ増え続けるのか
第3章 BIS規制と会計操作―金融危機はなぜ起こったか
第4章 デフレ―いったい誰が得したのか
第5章 ケインズ経済学の破綻―構造改革と景気
第6章 ペイオフ―預金を減らせ
第7章 郵貯民営化―国債はどこへ行く
第8章 金融立国試論―市場を生かせ
著者等紹介
桜川昌哉[サクラガワマサヤ]
1959年福井県生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。大阪大学大学院経済学研究科後期博士課程単位取得退学後、大阪大学経済学部助手、名古屋市立大学大学院経済学研究科教授を経て、慶応義塾大学経済学部教授。経済学博士
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
佐島楓
38
経済学を履修しようか迷っていた頃に読んだ本。デフレに対する新たな観方が得られ、ケインズについては自分なりにまとめてみたいと思えた。2015/09/22
ハンギ
0
あまり理解しているとは思わないけど、一読した。バブルの影響は金余りだったらしい、とか、構造改革の影響で経済が良くなったわけじゃない、とかいろいろと面白かった。もうちょっと金融を自由化することを唱えており、銀行や郵貯が国債を保有するのには厳しいお考え。銀行の自己資本比率規制の導入にあたっては、国は銀行に粉飾してもいいというお墨付きを与えたのはショックだった。預金者は銀行が倒産した場合、負債を全部かぶるべきだと言っていた。今の銀行には金利がつかないのに、銀行制度は預金者にどういうメリットがあるのか不思議。2012/05/04
-
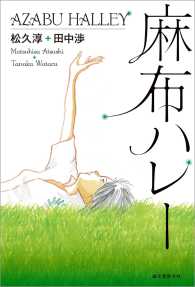
- 電子書籍
- 麻布ハレー