- ホーム
- > 和書
- > 児童
- > 創作絵本
- > 民話・神話・古典絵本
内容説明
隋の軍隊は、大きな川に行く手をはばまれる。そこに七人のじいさまが現れて…。
著者等紹介
水谷章三[ミズタニショウゾウ]
1934年、北海道に生まれる。人形劇団「プーク」を経て、劇団「太郎座」へ。瀬川拓男、松谷みよ子両氏の民話運動と出会う。現在、民話の再話、紙芝居の脚本、物語の創作などで活躍中。日本民話の会会員
遠山繁年[トオヤマシゲトシ]
1953年、長野県に生まれる。パリ国立美術学校でリトグラフを研究し、現在は油絵、水彩画、版画で創作活動を続けている。宮沢賢治挽歌画集「永訣の朝」で第44回産経児童出版文化賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Smileえっちゃん
49
図書館本。七世紀初め小さな国、高句麗は、巨大な隋の大軍に攻められ、村が焼け野原になる。隋は高句麗の都平壌を責めるにも、深くて流れの激しい清川江を渡らねばなりません。やっとここまで来たのにと立ち尽くす。そこに現れた白ヒゲの7人のおじいさん。次々と激しい川の中に入っていくと流れは静まり浅くなっていく。それを見て、「続け!」と20万の兵がなだれ込んでいくが…あの不思議なじいさまは誰だったのか?歴史上の事実があって生まれ、語り継がれた民話です。少し前、「武神」を見たところで興味がありました。2023/03/05
遠い日
16
韓国の民話。7世紀始めの朝鮮。高句麗を襲った大国の随を、七人の坊さまたちが、打ち破った不思議なできごと。戦争の愚かさとともに、戦いにひとたび巻き込まれてしまえば、どうにもならない理不尽な力関係に押さえつけられてしまう悲しさを感じる。今この時代だからこそ、戦うことの虚しさ、無意味さを子どもたちとともに考えたい。2015/12/04
みさどん
15
朝鮮半島の中で同じ民族が覇権を争って血を流す様子がもの悲しい。仙人のような超越した何かが攻められる国を救ったのだが、水に流されていった兵達も同じ民衆である。領土をかけた無益な戦いこそがばかげているのだ。北朝鮮がミサイルを打ち上げた今、本当に考えてほしいこと。イスラム国といい、おかしなことが本当に実行されていくことが恐ろしい。2016/02/12
絵本専門士 おはなし会 芽ぶっく
12
7世紀始めの隋が高句麗に戦争をしかけた事を基に、語りつがれてきた民話。清川江(チョンチョンガン)の岸辺にある七仏寺(チルブルサ)は、不思議なじいさまを忘れらないよう建立されたそうです。隋は『ずい』と読むのに、高句麗は『コグリョ』と読むんですね。習ったのは『こうくり』でしたが。朝鮮は1度として他の国を侵略したことのない国で、そのことを誇りに思っている国のようです。2019/10/26
ヒラP@ehon.gohon
4
七人のふしぎなじいさまたちが、隋の侵略から高句麗の国を守ったというお話です。 話がスッキリしているので、子どもたちにも分かりやすいお話ではあります。 ただ、このてのお話は国の歴史を伝えるか、国を守るというテーマをあらかじめ子どもたちに準備しておくかしないと、ただ聞いただけに終わって、印象に浅い絵本になってしまうのではないかと思いました。 読み手も歴史を勉強しないといけない絵本です。 2014/01/20
-

- 電子書籍
- 素直になれない雪乙女は眠れる竜騎士に甘…
-

- 電子書籍
- ミケとはなの終末(19) COMICア…
-

- 電子書籍
- 月刊サンデーGX 2024年7月号(2…
-
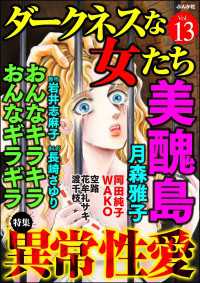
- 電子書籍
- ダークネスな女たち Vol.13 異常…





