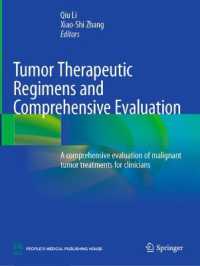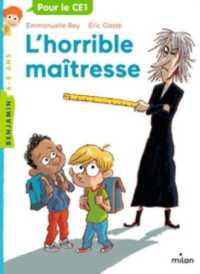目次
職人の道具として改造され尽くした建物―町工場(昭和二十二年築)
狭い間口に全長百二十メートルの唖然とする深さ―街道筋の商家(明治中期頃築)
DKの発想を日本人に教え込んだ住宅―団地(昭和四十年頃築)
一軒家の風格が詰まる連棟式幕の内弁当―二階建て長屋(大正末期築)
全自動湯沸かし浴場発祥の舞台裏―銭湯(昭和三十六年築)
柔の心で今なお営まれる二つの職場―町道場兼整骨院(昭和四十二年築)
ドヤ暮らし一畳ひと間テレビ付き―ベッドハウス(昭和二十四年築)
戦後混乱期の色香はいずこ―赤線建築(昭和二十年代前半築)
和風建築現場を支える「林場」が居並ぶ巨大商家―材木店(昭和二十六年築)
昭和のモダン鉄筋建築に内包された伝統生活―清洲寮(昭和七年築)〔ほか〕
著者等紹介
眞鍋じゅんこ[マナベジュンコ]
1959年東京生まれ。夫である鴇田康則と共に日本の過疎村や離島、ベトナムやタイを旅しながら農漁村・少数民族の生活を記録。一方で東京の人々の様々な暮らしやその住まいにも取材を重ねる。都市部における第一次産業、特に東京湾の漁師を数年来取材している
鴇田康則[トキタヤスノリ]
1954年東京生まれ。広告や雑誌、レコードジャケットなどの撮影と共に、アフガニスタンなど中央アジアや北米、タイ、ベトナムなどの人々の生活風景を写真に収めて歩く。眞鍋と共に日本の村や東京の町歩きの他、東京湾の漁師や村の暮らしを記録している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
-
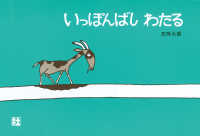
- 和書
- いっぽんばし わたる