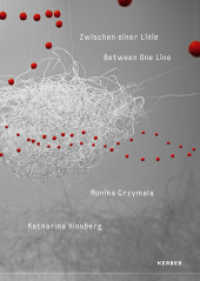内容説明
乗り物の側から見た移動でなく、人の側から、人と環境に配慮した移動。今、富山ではこうした考え方にもとづく、公共交通を軸にしたまちづくりが着々と進められている。日本列島の一地方に過ぎないこの地で、世界的な潮流となっている先進的公共交通政策がなぜ、どのように可能になっているのか。本書は、地元富山の行政機関や多数の交通関係者に取材し、その秘密を解き明かす。富山の試みは、果たして例外なのだろうか。
目次
第1章 富山は豊かである
第2章 昭和の改革者・佐伯宗義
第3章 なぜ富山は改革に乗り出したのか?
第4章 万葉線が奏でた序曲
第5章 奇跡のライトレール
第6章 高山本線で行こう
第7章 セントラムで都心を元気に
第8章 アヴィレという名の公共自転車
第9章 アルペンルートを貫光せよ
第10章 北陸新幹線開業を見据えて
著者等紹介
森口将之[モリグチマサユキ]
モビリティジャーナリスト・モータージャーナリスト。株式会社モビリシティ代表取締役。1962年東京都生まれ。早稲田大学卒業後、出版社編集部を経て、1993年に独立。国内外の交通事情を精力的に取材・視察し、地球環境や高齢化社会等、問題が山積した現代社会における理想のモビリティの探究・提案を続けている。日本カー・オブ・ザ・イヤー選考委員。日本デザイン機構理事。日本自動車ジャーナリスト協会会員、日仏メディア交流協会会員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。