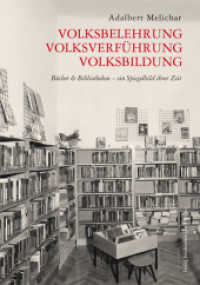内容説明
小説・詩の一節、映画のセリフ、著名人の言葉でドイツ語文法を学ぶ。気軽に読めて、ドイツの文化や歴史が見えてくる文法書。
目次
あいさつ―グリム・メルヒェン「赤ずきん」
発音(1)母音―映画『会議は踊る』
発音(2)子音―シラー「歓喜に寄せて」
名詞の性と冠詞(1)―ベルリンの壁崩壊のころ
名詞の性と冠詞(2)―ベルリン封鎖15周年とケネディ
最重要動詞(1)sein―ニーチェ「神は死んだ」
主語に合わせた動詞の変化(1)―デカルトとドイツ
主語に合わせた動詞の変化(2)―都市の空気は自由にする
最重要動詞(2)habenとwerden―ミヒャエル・エンデ『モモ』
ドイツ語文の語順―女優レーネ・ディートリヒ〔ほか〕
著者等紹介
矢羽々崇[ヤハバタカシ]
1962年岩手県盛岡市生まれ。ミュンヘン大学マギスター(修士)、上智大学博士(文学)取得。獨協大学外国語学部ドイツ語学科教授。専門は近現代ドイツ文学(主に叙情詩)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
84
初級者というよりも一通りドイツ語の基礎を学んだ人か私のように数十年前にドイツ語を学んだ人向きなのだと思いました。最初に短文のドイツ語が出てきて、それに伴い文法の基礎的なことかを説明してくれています。更にコラムなどで映画や文学などについて敷衍されていることもかなり参考になり楽しさが倍増します。無味乾燥な文法書ではないと感じました。2018/02/16
ゆーかり
16
“脱線中心、これで本当に覚えられるのかドイツ語文法” とある様に、名言名句、本や映画を紹介しながらの文法本。言葉の時代背景の説明などもあり読み物として面白い(文法は忘れてるので)。第二次大戦後間もない頃のエピソード、学者が話す外国語訛りの講義が聞き取りにくく飽きてしまった学生。それを見た学者がラテン語で話し始めると学生たちの目の色が変わってノートを必死に取り始めたという。意外と最近の出来事でびっくり。ドイツ語の時代による変化(発音や、英語と同じ様な変化をとげつつあるなど)も面白い。2018/02/04
Schuhschnabel
6
一通り文法は勉強したけども、細かいところはうろ覚えになっている感じの人が読むと面白いと思います。文法をこれから身に付けようという人は『しっかり身につくドイツ語トレーニングブック』のような数をこなしていくような本を選ぶのが、面倒くさそうで実は近道のような気がします。結構セリフの部分が多く引用されているのを見て、一年前に買って積読状態になっている"Momo"のセリフの部分だけ訳読していこうという気になった。2018/02/24
ががが
5
ドイツ語圏の言語文化からドイツ語の一節を取り上げて、そこに付随する文法事項を解説する本。全40課。想定読者は読み物としてのドイツ語に興味を持っている初学者とかつてドイツ語を勉強していた学習者。ドイツ語学習の副読本として活用するのがいいだろう。文法事項も十分に解説してあるが、文化的な小ネタだけを拾い読むことも可能な構成で、全体として通読できる文法書を目指して書かれているように思われる。気軽に読めるのだが、そのやり方で行くと後半の文法説明が難しい。邦訳されていないドイツ語圏の作品も多いのだなと気づかされる。2024/01/08
小雪
5
やっと、やっと終わりましたよ…三週間かかって、やっと読み終わった…。というより学習し終わった…。ドイツ語をこの前から習い始めたのですが、非常に楽しくドイツ語を学べる本になっています。40課からなる濃密な初級独文法で、それなのに、惜しみもなくドイツの思想家の名言に触れることができます!なんてことだ!ドイツ語これからも頑張る!2018/02/24
-

- 洋書
- HARCELEUSE