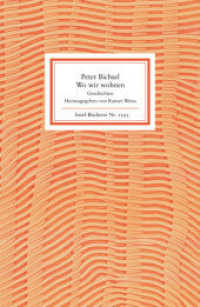出版社内容情報
東海地方の地域づくりを軸にした、歴史的社会的「点描」群。連続する時空の社会現象の歴史的意味と社会的位置を推測する。
はじめに
第一部
第一章 豪農竹村広蔭にみられる江戸末期の規範意識 大橋博明
はじめに
一 広蔭が置かれた家政・村政に関わる状況
二 広蔭と学問
三 広蔭の規範意識
おわりに
第二章 幕末における和学者八木美穂の教育活動 大橋博明
はじめに
一 八木家の課題と美庸の生活規範
二 美穂の学究の過程
三 教育の目的
四 教育の内容
五 教育活動の様態
おわりに
第三章 明治への過渡期の教育 大橋博明
──豊橋藩漢学寮・皇学寮と三河県修道館を事例として──
はじめに
一 漢学寮
二 修道館
三 皇学寮
おわりに
第二部
第四章 中山間地域における地域づくりと住民 赤坂暢穂
──岐阜県旧加子母村を事例として――
はじめに
一 岐阜県旧加子母村の概況と地域づくりの特徴
二 地域づくりの経緯
三 地域づくりの現状と課題
おわりに
第三部
第五章 偽装リサイクル製品としてのフェロシルトと不法投棄の隠蔽工作 ましこ・ひでのり
はじめに
一 事件の背景と経緯
二 社会問題化後の経緯と事件の構図
三 事件の本質
おわりに
第六章 『岐阜県史』問題再考 ましこ・ひでのり
──産廃行政に関する「県史」等の記述の政治性――
はじめに
一 事態の経緯
二 問題の本質
三 『御嵩町史 通史編 現代』の刊行
おわりに
内容説明
本書は東海地方の地域づくりを軸にした、歴史的・社会的「点描」群である。
目次
第1部(豪農竹村広蔭にみられる江戸末期の規範意識;幕末における和学者八木美穂の教育活動;明治への過渡期の教育―豊橋藩漢学寮・皇学寮と三河県修道館を事例として)
第2部(中山間地域における地域づくりと住民―岐阜県旧加子母村を事例として)
第3部(偽装リサイクル製品としてのフェロシルトと不法投棄の隠蔽工作;『岐阜県史』問題再考―産廃行政に関する「県史」等の記述の政治性)
著者等紹介
大橋博明[オオハシヒロアキ]
1940年生まれ。東京大学大学院。中京大学教養部教授(教育学)。中京大学文化科学研究所員
赤坂暢穂[アカサカノブオ]
1941年生まれ。明治大学大学院。中京大学教養部准教授(地理学)。中京大学文化科学研究所員
ましこひでのり[マシコヒデノリ]
1960年生まれ。東京大学大学院。中京大学教養部教授(社会学)。中京大学文化科学研究所員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。