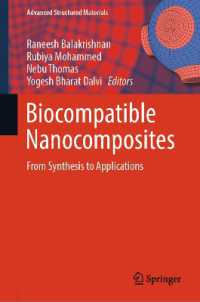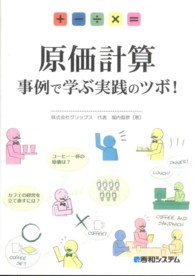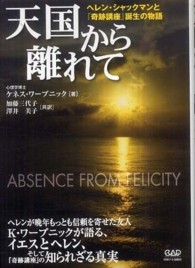内容説明
2025年、年間150万人が死亡する時代。病院を中核とするこれまでの医療供給システムは通用しない。超高齢社会に望ましいヘルスケアをどう構築すべきか。国内外のデータと日本各地の先進事例から、将来必要になる枠組みを示唆。
目次
第1部 医療のなにが問題なのか(社会保障制度と支払い方式;各国の医療保障制度;日本の医療保障制度;医療のなにが問題なのか)
第2部 超高齢社会日本の医療モデル(医療システムの新しい潮流―予防医療システムの展開;ヨーロッパの医療制度改革から学ぶ;日本の医療制度改革の方向―平成18年度医療制度改革とその後の改革案;超高齢社会日本の医療モデル:4つの重要領域;改革の理念と「既に起こっている未来」)
医療制度改革への提言
著者等紹介
松田晋哉[マツダシンヤ]
1960年岩手県生まれ。1985年産業医科大学医学部卒業。1991年‐1992年フランス政府給費留学生。1992年フランス国立公衆衛生学校卒業。1993年京都大学博士号(医学)取得。産業医科大学医学部公衆衛生学講師を経て、産業医科大学医学部公衆衛生学教授。専門領域:公衆衛生学(保健医療システム、医療経済、産業保健)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
hurosinki
6
かなり専門的な内容も含むが、医療情報の収集やそれを活用した医療計画の策定について詳しい。欧米(特にフランスとオランダ)の医療制度についても紹介しているので興味がある人は是非。フランスの医学部は1年終了時に厳しい選抜があり、2年に進級できるのは5分の1という記述には目を疑った(p174)。医療費適正化の手法として診療報酬の役割を強調する池上氏と異なり、筆者は(診療報酬の改訂よりむしろ)医療計画を通じて医療提供体制を改革していくことで財政制約に対応すべきとしている(p121)。2021/12/31
Takeshi Watabe
0
医療体制の抱える問題を再整理できた。2015/07/02
coldsurgeon
0
少子化高齢化により日本社会が直面する問題を、どう考えていくか。病院を中核とするこれまでの医療供給システムは通用しないことを認識している医療者は、特に医師は、少ないのではないかと思う。医療や介護は社会インフラであり、それらの情報化を進めて、適切に「既に起こっている未来」を認識すべきであろう。「我々は人の役に立つ仕事をしている」という自負が強すぎると往々にして、自己中心的で一方的なサービスを提供しがちになり、顧客の支持を得られなくなってしまう」というドラッカーの言葉を肝に銘ずる。2014/08/22
ラピスラズリ
0
非常にバランスの取れた素晴らしい本だった。特定の誰かだけに課題がある、改善が必要と言及するのではなく、政府、国民、医療関係者それぞれに改善点があることがよく分かった。この本が書かれた当時(2013年)はまだマイナンバーの導入は決まっていなかったと思うが、マイナンバー制度を利用した医療情報の共有が、それぞれの地域の医療資源の配分戦略、ひいては社会保険料削減のためにいかに重要であるかがよく分かった。2023/07/26