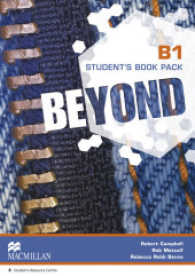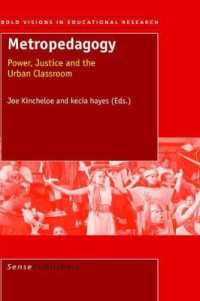内容説明
なかなか内定を獲得できない学生は大学の就職斡旋に頼ってみるのも一手かもしれない。実は結構役に立っている支援プログラムの姿を描き出す。
目次
第1章 新規大卒労働市場における大学就職部
第2章 斡旋からガイダンスへ―大学就職部業務の歴史的変遷
第3章 就職斡旋における大学就職部の役割―学生の選抜・企業の選抜
第4章 誰が大学就職部を「利用」するのか―機会という観点からの分析
第5章 誰が大学就職部を「経由」するのか―斡旋を受ける機会
第6章 大学就職部「経由」の効果
終章 セーフティネットとしての大学就職部
著者等紹介
大島真夫[オオシママサオ]
1974年生まれ。2006年東京大学大学院教育学研究科博士課程単位取得退学、博士(教育学)。現在、東京大学社会科学研究所助教(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
きいち
2
論文なので、わかったことだけじゃなく、言えないこと、わからなかったこと、あえて証明しなくてもそりゃそうだろう、というようなことも合わせてちゃんと記述してある。何より、大学就職部がまずはすべての学生に開かれていて、かつ晩期まで決まらなかった学生が良質ではない進路を選ばずに済むセーフティネットとして機能していることが主張できていればそれでよい。自分にとっては既知の分野で、かつ久しぶりのフルフル学術論文だったので、うーん、まだるっこしさを堪能できた感じ。良質な論文だったし、まあ、たまにはいいか、そんなのも2012/09/22
壱萬参仟縁
1
大学は学生に対する教育機関であると同時に就職斡旋機関である(200ページ)。OBとかOGには関係ないか。ホントはむしろ卒業生にも便宜があってもいいと思えるご時世であるのが評者の本音であるが。ま、ハロワで探す以外なかろう。あるいは、マイナビ転職サイトか(苦笑)。著者は社会教育学が専攻のようだ。岩波書店はコネ採用を公然と宣言して学生の就活を求めた。これも厳しい世の中、信用が第一になってきている証か。結局、人間だから。今、テレフォン人生相談で加藤諦三先生が「人間関係で大切なのは無意識」とおっしゃった。ほほぅぅ。2013/01/21
YH
0
「学生の自立を促しながらも、最後の最後まで学生に寄り添うのが私たちの仕事の一丁目一番地」課長が常に言っている言葉が身に染みた。 以下、抜粋。 ・就職活動シーズン早期に就職が決まらなかった学生、つまり就職戦線における弱者を救済するセーフティネットとしての役割を果たしているp29-30 ・晩期における就職斡旋の充実こそが、まだあまり注目をされていないけれども取り組む価値のある「大学就職部にできること」だとわたしは信じているp2162017/11/18