出版社内容情報
マックス・ヴェーバーは、はたして社会学者か。没後百周年を前に、ヴェーバー社会学創成の理由と意味を問い直す。著者年来の『経済と社会』再構成論に即した入門編。
「歴史・社会科学における基礎研究と応用研究との相互交流」を実りあるものにするにはどうしたらよいか。「ヴェーバー社会学」は、自己目的的な専門学科ではなかった。この問いとむきあった「歴史研究への基礎的予備学」であったのだ。「理解社会学のカテゴリー」論文を体系的に読み、なぜ彼が「社会学」を必要としたのかを考察する。
はじめに――問題提起
第一章 「カテゴリー論文」
――思想諸潮流の相互媒介による社会学の定礎と基礎概念構成
第二章 ヴェーバー社会学の創成と本源的意味
――歴史科学研究への基礎的予備学
第三章 ヴェーバー社会学における「正当性」問題
――歴史・社会科学における基礎論と応用研究との相互交流に向けて
あとがき
索引/著者略歴
内容説明
ヴェーバー社会学が「生まれ出る姿で」蘇る。半世紀にわたって、「これを耕して尽くさず」と、ヴェーバー『経済と社会』の読解に沈潜してきた著者が、何よりも読者のヴェーバー「活用」を願って、ここに初めて提示する、体系構成の基礎と骨子。
目次
第1章 「カテゴリー論文」―思想諸潮流の相互媒介による社会学の定礎と基礎概念構成(「方法的個人主義」にもとづく「社会形象」の分析的・動態的説明方針:「社会科学方法論争」の一止揚形態;「自由な」「合理的」行為の戦略的意義:さまざまな「非合理」の索出経路;「正当性」論の思想的源泉:マルクス「イデオロギー論」とニーチェ「ルサンチマン論」との相互媒介による一止揚形態 ほか)
第2章 ヴェーバー社会学の創成と本源的意味―歴史科学研究への基礎的予備学(「客観性論文」における「社会学」へのスタンス;社会科学の四階梯構想と「現実科学」の「法則科学」的成分;「倫理論文」の研究手順とその「現実科学」的・「歴史科学」的性格 ほか)
第3章 ヴェーバー社会学における「正当性」問題―歴史・社会科学における基礎論と応用研究との相互交流に向けて(水林論文の要旨;水林説の正しさ;敷衍したい二点:「正当性」論の体系的位置と「潜勢」 ほか)
著者等紹介
折原浩[オリハラヒロシ]
1935年生まれ。1958年東京大学文学部社会学科卒業。1964年東京大学文学部助手、1966年東京大学教養学部助教授を経て、1986年東京大学教養学部教授。1996年名古屋大学文学部教授、1999年椙山女学園大学人間関係学部教授ののち、2002年に同学部を退職。東京大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 電子書籍
- 恋愛レベル99の男、落とします【ページ…
-

- 電子書籍
- 闇金ウシジマくん【タテカラー】 サラリ…
-
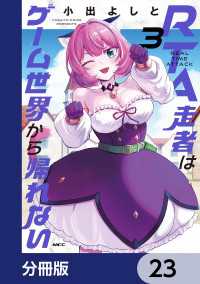
- 電子書籍
- RTA走者はゲーム世界から帰れない【分…
-

- 電子書籍
- ストーカーに抱かれて 分冊版 11 ア…
-
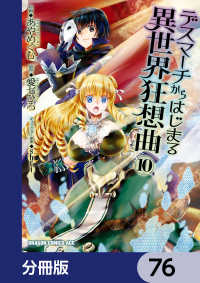
- 電子書籍
- デスマーチからはじまる異世界狂想曲【分…




