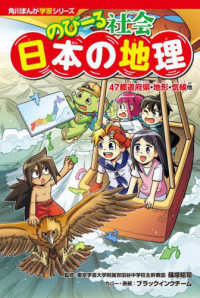出版社内容情報
この新しいロジックは、世界をどう変えるのか。
生物多様性戦略は画餅にすぎないか。
COP10後の日本社会を見据え、法制度の創造的活用を説く。
【内容】
生物多様性というロジックは、社会の基盤たる法制度にどのように投影されているか。この理解なしに、今後の社会のあり方を論じることはできない。法の意義から具体的な地域戦略策定の手法まで、わかりやすく説く本書は、「制度生態系」や「環境の司令塔」など最先端の議論も展開。自治体やNPO、企業人も必読の“市民のための専門書。”
【3つの特徴】
★1★ よりどりみどりの生物多様性本。でも、この視点は本邦初!
従来の生物多様性本は、生態保全学やビジネス、データ把握に主眼を置いたものが多かった。しかし本書では、生物多様性という「ロジック」に注目。大局的な視点で社会を俯瞰する。
★2★ 自治体・まちづくりの現場を変革するシナリオは、ここから始まる。
10月のCOP10後に、全国各地の自治体で生物多様性「地域戦略」の策定が加速的に進むことが予想されるが、各自治体で具体的にどのような地域戦略をつくるべきか。生物「多様性」という言葉どおり、“金太郎アメ”的ではなく、各地域の持ち味を生かした戦略づくりができるよう、実践的な提言を行っている。
★3★ 「ハーバード白熱教室」にも負けない、分かりやすさと面白さ
それぞれの章・節ごとに、Episode とQuesetionから導入。「生物多様性」に関わる最近の時事問題など身近な例から興味をひきつけ、法制度に日頃はなじみのない初学者にも、とても分かりやすく工夫した書きぶり。
一方で、アジアの地域戦略策定状況や、アメリカの「環境の司令塔」システムなど、先進的な議論も展開。章末には、さらに研究を深めたい人のための注、引用文献も充実し、研究者にもオススメ。
【目 次】
はじめに
本書の特徴
第1章 生物多様性とはなにか
第1節 生物多様性とはなにか
第2節 生物多様性プラットフォームの誕生
第2章 生物多様性はルールにできるのか
第1節 制度生態系の成立
第2節 進化する自然保護法―生物多様性の保全
第3節 環境法化する諸法
第3章 ロジックは世界をどう変えるか
第1節 生態リスク管理と自然再生
第2節 衡平性の確保―ABSとSATOYAMA(里山)
第3節 生物多様性の確保と「司令塔」
第4章 なぜ戦略をつくるのか
第1節 日本の生物多様性戦略
第2節 ニュージーランドの地域戦略
第3節 地域戦略の技法─資源創造と参加型生物多様性評価
付録:関連法令情報について
読者のみなさんへ
索引
目次
第1章 生物多様性とはなにか(生物多様性とはなにか;生物多様性プラットフォームの誕生)
第2章 生物多様性はルールにできるのか(制度生態系の成立;進化する自然保護法―生物多様性の保全;環境法化する諸法)
第3章 ロジックは世界をどう変えるか(生態リスク管理と自然再生;衡平性の確保―ABSとSATOYAMA(里山)
生物多様性の確保と「司令塔」)
第4章 なぜ戦略をつくるのか(日本の生物多様性戦略;ニュージーランドの地域戦略;地域戦略の技法―資源創造と参加型生物多様性評価)
著者等紹介
及川敬貴[オイカワヒロキ]
1967年北海道に生まれる。2000年北海道大学大学院法学研究科博士課程修了(法学博士)。現在、横浜国立大学大学院環境情報研究院准教授。環境法専攻(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 電子書籍
- 日本の歴史を動かした女たち 中経の文庫