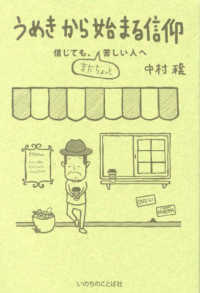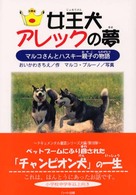出版社内容情報
国の事業ばかりでなく地方団体においても必須となってきている費用便益・分析の解説本。多くの国・地方の公務員、シンクタンクの実務者、学生にとって必読。
本書は、費用・便益分析の基礎としての経済学的概念、厚生経済学的基礎から費用・便益分析の方法論・応用までが書かれており、費用・便益分析の基礎を理解して現実の問題に適用できるように構成されている。本書1冊を読むだけで費用・便益分析の基礎を理解して現実の問題に適用することができる。
[関連書] D.ヴォース 『入門リスク分析』 (勁草書房刊)
第1章 序
1.1 CBAの理論的基礎と根拠
1.2 CBAの応用:小史
1.3 本書の構成
1.4 要 約
1.5 討論のための問題
第2章 経済効率性,所得分配,市場メカニズム
2.1 効率性基準:パレート最適
2.2 パレート最適と社会厚生関数
2.3 市場で決まる配分と効率性
2.4 要 約
2.5 付録:生産と交換における効率性条件
2.6 討論のための問題
第3章 市場の失敗,経済的効率性,および集団的意思決定
3.1 公共財が存在する場合の効率性
3.2 外部性が存在する場合の効率性
3.3 不完全競争が存在する場合の効率性
3.4 集団的意思決定ルール
3.5 要 約
3.6 討論のための問題
第4章 費用・便益分析の基本
4.1 典型的な費用・便益の設計
4.2 費用・便益分析の段階
4.3 費用・効果分析
4.4 要 約
4.5 討論のための問題
第5章 公共プロジェクトの配分効果
5.1 消費者余剰
5.2 補償変分と等価変分
5.3 生産者余剰
5.4 プロジェクトの便益と費用
5.5 要 約
5.6 付録:効用の差の測度
5.7 討論のための問題
第6章 費用と便益の計測
6.1 最善および次善分析
6.2 生産要素の価値
6.3 要 約
6.4 討論のための問題
第7章 非市場価値評価
7.1 生命の価値
7.2 時間価値
7.3 仮想市場評価法
7.4 要 約
7.5 討論のための問題
第8章 投資基準とプロジェクト選択
8.1 純便益の割引
8.2 決定基準の選択
8.3 リスクと不確実性
8.4 要 約
8.5 討論のための問題
第9章 割引率の選択
9.1 最善と次善の状況における割引
9.2 割引の実際
9.3 要 約
9.4 討論のための問題
第10章 評価基準としての所得分配
10.1 効率性および公平性とプロジェクト評価
10.2 分配の重み付け
10.3 要 約
10.4 付録:分配ウェイト
10.5 討論のための問題
第11章 費用・便益分析の適用
11.1 費用・便益分析の問題点:要約
11.2 費用と便益の確認のための一般的ルール
11.3 現実世界への適用におけるCBAの設計
11.4 規制代替案の経済学的分析
11.5 要 約
11.6 討論のための問題
第12章 評価研究:環境
12.1 環境の評価問題
12.2 環境プロジェクトの費用・便益分析
12.3 要 約
12.4 討論のための問題
第13章 評価研究:健康管理
13.1 健康管理における評価問題
13.2 要 約
13.3 討論のための問題
第14章 発展途上国のCBA
14.1 基礎理論
14.2 UNIDOガイドラインと世界銀行モデル
14.3 世界価格手法の現実への適用
14.4 要 約
14.5 討論のための問題
参考文献
監訳者あとがき
索 引
内容説明
国の事業ばかりでなく地方団体においても必須となってきている費用・便益分析の解説本。本書1冊を読むだけで費用・便益分析の基礎を理解して現実の問題に適用することができる、多くの国・地方の公務員、シンクタンクの実務者、これから社会にでる学生にとっての必読本。
目次
経済効率性、所得分配、市場メカニズム
市場の失敗、経済的効率性、および集団的意思決定
費用・便益分析の基本
公共プロジェクトの配分効果
費用と便益の計測
非市場価値評価
投資基準とプロジェクト選択
割引率の選択
評価基準としての所得分配
費用・便益分析の適用
評価研究:環境
評価研究:健康管理
発展途上国のCBA
著者等紹介
萩原清子[ハギワラキヨコ]
東京都立大学都市研究所助教授(1991‐1993年)・東京都立大学大学院都市科学研究科教授(1993‐2006年)、京都大学防災研究所水資源研究センター客員教授(1996‐1998年)。佛教大学社会学部公共政策学科教授・工学博士。東京都立大学・首都大学東京名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。