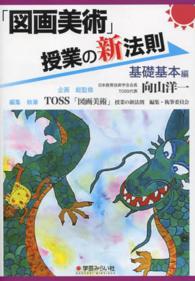出版社内容情報
今日、「国民国家」の枠組が大きく揺らぎ、従来の「国民」「国民主権」といった概念が変容しようとしている。日本でも外国人の参政権という形で改めて 「国籍」概念が問われつつある。
本書は以上の問題意識を踏まえ、奴隷制、ネイティブ・アメリカン問題や他方で1928年まで外国人に選挙権が認められてきたこと、また2001年9月11日のテロ以降の移民政策規制強化を進めるアメリカに焦点を当て、独立以来のその市民権(国籍)のあり方を歴史的に分析する。
【主な著書】『憲法四重奏』(共著、有信堂高文社、 2002)、卜ーマス・ハンマー(近藤敦監訳)『永住市民(デニズン)と国民国家』(共訳、明石書店、 1999)
序章 問題の所在と課題の設定
第Ⅰ部 新しい市民権概念の形成
──革命前期のイギリスとの論争を通じて──
第1章 イギリスにおける伝統的な臣民権の理論
第2章 独立革命前期のイギリス─アメリカ間の論争
第3章 アメリカにおける「国家」と「国民」
第Ⅱ部 矛盾の顕在化と市民権概念の確立
──黒人・インディアンの法的地位と修正第14条の制定──
第1章 黒人の法的地位
第2章 南北戦争と修正第14条の制定
第3章 インディアンの法的地位
まとめ アメリカ「国民国家」の枠組みの成立
第Ⅲ部 市民権概念をめぐる諸制度の変遷
──「移民国家」アメリカと外国人の権利──
第1章 アメリカにおける移民政策の変遷
第2章 移民政策に関する判例
第3章 外国人の権利に関する判例
第4章 定住外国人の参政権
まとめ ナショナリズムの形成と外国人への対応の変化
終章 まとめと展望
人名索引
事項索引
判例索引
内容説明
「国民」とは一体誰か?「移民国家」アメリカの植民地時代から現代までを憲法史的にアプローチし、アメリカにおける国籍・市民権概念の歴史的変遷のダイナミズムを浮き彫りにする。「国民国家」再検討のための基礎的研究。
目次
問題の所在と課題の設定
第1部 新しい市民権概念の形成―革命前期のイギリスとの論争を通じて(イギリスにおける伝統的な臣民権の理論;独立革命前期のイギリス―アメリカ間の論争 ほか)
第2部 矛盾の顕在化と市民権概念の確立―黒人・インディアンの法的地位と修正第14条の制定(黒人の法的地位;南北戦争と修正第14条の制定 ほか)
第3部 市民権概念をめぐる諸制度の変遷―「移民国家」アメリカと外国人の権利(アメリカにおける移民政策の変遷;移民政策に関する判例 ほか)
まとめと展望
著者等紹介
高佐智美[タカサトモミ]
1969年生まれ。法学博士。現在、独協大学法学部国際関係法学科専任講師
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。