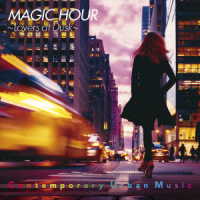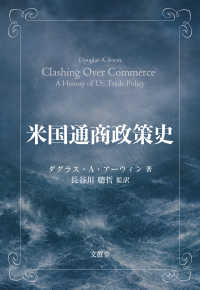出版社内容情報
今日「文化」は、あらゆる政策の中核理念となり、政策横断的な共通項として認識されるようになった。そして「文化政策」は、各種政策を収斂する総合政策としての色彩を強めようとしている。この21世紀において、文化政策はますます重要な政策領域となることが予想される。このような状況を背景に、近年、多くの大学で文化政策に関わる授業科目が開講され、いくつかの大学では、独立の文化政策関係学部も設置されるようになった。そのような動きの中で、「文化政策学」の確立が急がれる状況となっており、本書の刊行はまさに時期を得たものといえる
目次
序章 「文化政策学」構築の視点
第1章 文化政策の変遷
1 戦前
2 戦後の第1期(終戦から1950年代末)
3 戦後の第2期(1960年代から1970年代前半)
4 戦後の第3期(1970年代前半から1980年代末)
5 戦後の第4期(1990年代以降)
第2章 文化政策の背景
1 内容不関与の原則
2 「文教」政策の一環への位置付け
3 日本文化の形成過程との関連
4 1980年代の時代状況
第3章 文化政策の構造
1 国(文化庁)の文化政策の対象領域と機能
2 文化の振興と普及
3 他の政策領域の文化への接近と文化政策
4 地方公共団体の文化政策
5 文化法制と文化予算
第4章 文化政策の形成過程と政策策定機関による提言
1 文化政策の形成過程
2 震災と兵庫県の文化政策への影響
3 文化政策策定機関による諸提言
第5章 文化施設の設置・運営―設置者行政
1 文化会館
2 美術館
3 マネージメントの確立に向けて
第6章 アートマネジメントと文化政策
1 民間企業の文化へのアプローチ
2 文科経済学とアートマネジメント
3 アートマネジメントと文化政策の関連
第7章 まちづくりと文化政策
1 文化施設と都市景観
2 地方公共団体の文化政策の理念と政策展開の方向
3 文化を核としたまちづくりによる地域活性化の試み
第8章 歴史的・文化的景観に関わる文化財保護政策と関連諸政策の交錯
1 文化財と歴史的・文化的景観
2 自然的名勝及び天然記念物をめぐる文化財保護法と自然環境保全法制
3 文化財保護政策と各種政策の複合
第9章 田園景観をめぐる文化政策と各種政策のインターフェース
1 田園への開眼
2 田園の構成美と日常景の再認識
3 人文的景観と各種政策のインターフェース
第10章 文化政策の今後の方向
1 文化政策の背景にある2つの方向
2 芸術文化政策における新たな課題
3 文化政策の深化と範囲の拡大
4 総合文化政策の確立
参考図書・文献
索引
内容説明
「文化政策学」確立の方向性を探る。「文化政策」は、今日、「文化」を中核理念とする各種政策の重要な一領域を構成する。本書は、学問体系としての「文化政策学」の確立を目指すとともに、今後の充実した「文化政策」への指針として実際的な提言を行う。
目次
序章 「文化政策学」構築の視点
第1章 文化政策の変遷
第2章 文化政策の背景
第3章 文化政策の構造
第4章 文化政策の形成過程と政策策定機関による提言
第5章 文化施設の設置・運営―設置者行政
第6章 アートマネージメントと文化政策
第7章 まちづくりと文化政策
第8章 歴史的・文化景観に関わる文化財保護政策と関連諸政策の交錯
第9章 田園景観をめぐる文化政策と各種政策のインターフェイス
第10章 文化政策の今後の方向
著者等紹介
根木昭[ネキアキラ]
1943年岡山県生まれ。1965年大阪大学法学部卒業。文部省、外務省、文化庁を経て現在長岡技術科学大学教授。博士(法学)。文化経済学会理事。文部省・教育職員養成審議会臨時委員。文化庁・アーツプラン21企画委員会委員。他。著書に『文化政策論』(共著、晃洋書房、1996年)『文化会館通論』(共著、晃洋書房、1997年)『美術館政策論』(共著、晃洋書房、1998年)『田園の発見とその再生―「環境文化」の創造に向けて―』(共著、晃洋書房、1999年)他
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。