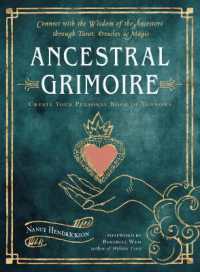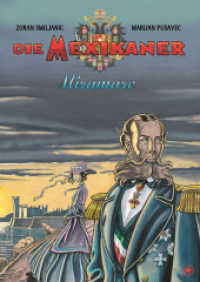- ホーム
- > 和書
- > 教育
- > 特別支援教育
- > 知的障害・発達障害等
出版社内容情報
LD、ADHD、高機能自閉症などの学習者の多様な二一ズに応える特別支援教育政策は、どう進められ、今後どう展開されるか。
特殊教育から特別支援教育への転換を図る──という文科省の提言(2003年1月)により、従来の特殊教育の対象だけでなく、LD(学習障害)、ADHD(注意欠陥/多動性障害)、高機能自閉症の児童生徒へと支援の対象が広まった。また通常教育の側でも、個に応じた指導を充実させる方向がめざされている。学習者の多様なニーズに応える政策を現場から明示する。
関連書 同著者 『学習障害(LD)──理解とサポートのために』(中公新書)
Ⅰ
第一章 特別な教育的ニーズを巡る経過
1 「特別な教育的ニーズ」の誕生
2 障害のある児童生徒への教育の歴史
3 「辻村答申」から「今後の特別支援教育の在り方」へ
第二章 定義と判断基準の明確化
1 定義と判断基準を明確にする意図
2 定義
3 判断基準(試案)
第三章 全国実態調査の結果
1 全国実態調査の意図
2 全国実態調査の目的・方法
3 全国実態調査の結果・考察
4 全国実態調査を受けて
第四章 指導法の確立に向けて
1 指導方法の確立の必要性
2 研究開発学校での取り組み
3 国立特殊教育総合研究所の研究成果から
Ⅱ
第五章 「最終報告」の提言─特殊教育から特別支援教育への転換─
1 報告の取りまとめまでの経過
2 特別支援教育とは
3 基本的な考え
4 学校の在り方
5 専門性の強化
第六章 モデル事業の展開─支援体制の構築─
1 モデル事業等の経過(平成11年度以前)
2 LDモデル事業の成果と課題
3 新規モデル事業の概要
4 特別支援教育コーディネーターの指名と養成
第七章 ガイドラインの策定
1 策定の趣旨
2 ガイドラインの構造と内容
3 ガイドラインの活用
第八章 自治体の取り組み
1 支援体制の構築
2 教職員の研修
3 理解推進や指導用の冊子の作成
4 教育センターにおける調査研究
5 自治体としての目標や計画の明確化
第九章 特別支援教育体制の整備状況のモニター
1 モニターの目的と方法
2 モニターの結果
3 モニターの結果から分かること
第十章 教育全体の動向と特別支援教育
1 文部科学省関係
2 厚生労働省関係
3 環境省関係
4 内閣府関係
終章 展望
1 すべての学校における支援体制の構築
2 LD・ADHD・高機能自閉症の指導方法の確立
3 政策連携の推進
4 企画・実行・評価のサイクルの推進
5 学習者の多様なニーズに応える教育の実現
補論 諸外国の動向及びWHO・ICFの概要
1ノルウェー 2マレーシア 3ニュージーランド 4カナダ
5イギリス 6ザンビア 7ドイツ 8オーストラリア 9韓国
10アメリカ 11WHO・ICFの概要
あとがき──ブランドイメージの構築
年表
資料
文献
索引
内容説明
質の高い適切な特別支援教育体制を構築するために。多様なニーズに応えるしなやかな教育の実現に向けた取組を紹介。
目次
第1章 特別な教育的ニーズを巡る経過
第2章 定義と判断基準の明確化
第3章 全国実態調査の結果
第4章 指導法の確立に向けて
第5章 「最終報告」の提言―特殊教育から特別支援教育への転換
第6章 モデル事業の展開―支援体制の構築
第7章 ガイドラインの策定
第8章 自治体の取り組み
第9章 特別支援教育体制の整備状況のモニター
第10章 教育全体の動向と特別支援教育
終章 展望
補論 諸外国の動向及びWHO・ICFの概要
著者等紹介
柘植雅義[ツゲマサヨシ]
1958年愛知県に生まれる。1983年愛知教育大学大学院修士課程修了。1988年筑波大学大学院修士課程修了。1995年筑波大学から博士(教育学)の学位取得。名古屋市公立学校教員、国立特殊教育総合研究所研究室長、カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)客員研究員を経て、現在、文部科学省初等中等教育局特別支援教育課・特別支援教育調査官(LD・ADHD・高機能自閉症等を担当)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。