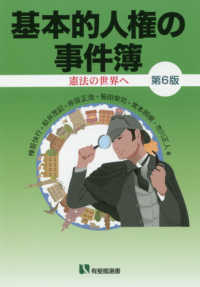出版社内容情報
「子どもがコントロールできない」「教師に権威を感じない」状況で、教師は子どもの成長とどうかかわるか。80年代以後の子どもの変容を考える時、教育装置が問題となる。教育方法論ではもはや教育問題は解決できない。社会が機能的分化の道をつき進み、教育そのものが成立しにくくなる現実。一方で近代的教育学の枠組の再考も求められている(フーコー、デリダ、ルーマン)。機能システムに寄生し、物の因果律、人の自律性、知の確実性を幻想する──
この過ちに気づき、社会的現実を相対化する知を構想せねばならない。それは関係の冗長性と
内容説明
教育装置、近代的教育学の枠組が大きく揺らいでいる現在、どんな教育、どんな教師が求められるのか。社会の機能的分化の進行と80年代以降の子どもの変容。
目次
序論 教育システムに寄生する―他者を喪う社会
第1章 喪われる権威―なぜ教育は難しいのか
第2章 伝達という幻想―言葉は伝わらない
第3章 教授のない教育―むだはむだではない
第4章 喪われゆく他者―匿名性が生みだす暴力
第5章 他者への教育―ニヒリズムを反転させる脱構築
第6章 存在を感受する―悲劇の感覚、驚異の感覚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
有智 麻耶
1
全面的な機能的分化の展開は、一方では近代の教育装置を解体させ、他方では子どもの他者性を喪失させてきた。このような状況において、教師は権威を喪失してしまう。しかし、それだからこそ、これまで自明の理のごときものとされてきた教授による教育から、社会的コミュニケーションによる学びへと転換する可能性が生じるという。ときに教育評論っぽさが顔を覗かせるのは、前近代の対面的共同体をどこか理想的に実体化してしまっているからだろう。いま読み返すと、この頃から田中智志だったのだと思わされる。2024/08/18
有智 麻耶
1
4年前に読んで以来、「他者」という概念に引き込まれ、卒論「他者」概念をテーマにして書いた。今、読み返してみると、5章を除いて、田中氏が「他者」をどのレベルの概念として扱っているのかがよくわからなかった(実在概念・集合概念・方法概念)。また、ポップ感覚と浮遊感覚は、物語消費とデータベース消費という消費のあり方にそれぞれ対応していると考えられるが、それだと田中氏の時代区分とややズレる。政治哲学から「他者」概念にアプローチするためのヒントは得られないが、根底で支えてくれている研究である。2018/03/10
hayaok
1
ルーマンの概念などを借用し、位階性が消滅し機能主義への移行がさらに進む中で教師の権威が落ちるのは必然であるから、そこで子どもを思うように教育する操作主義の放棄が必要だと説明する。来るべき社会の像として機能主義一辺倒ではなく、各人が他者の個体性と関係の冗長性、人生の悲劇性を認めていることという条件を提示し、そのために生の偶有的・刹那的な共在という了解―それは、従来の存在神学を超えたハイデガー的な存在論―と、それを喚起するような「驚異の感覚」を与える教育を提案する。2012/01/26
有智 麻耶
0
ポストモダンにおける教育改革や、社会の変容、近代批判の哲学を読んでから読み返すと、視界が開けた。それと同時に、いくつかの疑問も。ハイデガーの哲学に他者がいないというレヴィナスの批判に対し「気遣い」の概念で対抗しているが「気遣い」は他者を他人としても可能ではないのか。また、ヴィトゲンシュタインの言語ゲーム論の他者が同化の対象であるという主張も、何か定まった規則があり、それに従うことがコミュニケーションを成り立たせる、というような、旧来の、言語ゲームのダイナミズムを無視した発想に基づいているように見える。2016/01/04
有智 麻耶
0
再読。有用性に支配された社会では関係の冗長性が消え、他者の存在を感受することができなくなる。しかし、子どもを他者から他人に還元することは、コロニアリズム的である(丸山)、と内容を整理。また、言語ゲームで教育学的な他者を捉えることが別の支配体系を生み出すから、ハイデガー的な偶有的・刹那的な存在論を前提にするべき、という内容を新たに汲み取った。ルーマンやデュルケムを読まなくては。2015/02/13
-
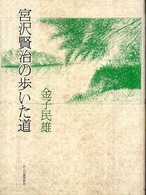
- 和書
- 宮沢賢治の歩いた道