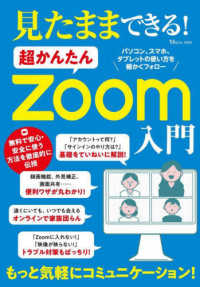出版社内容情報
認知科学や脳科学によって「心の働き」の探求が急速に進展している現在、そうした科学の知見を養分として、哲学の立場から心の本性に迫る「心の哲学」が盛んになってきている。現代哲学の最先端とも言える心の哲学の全貌を初めて紹介する待望の入門書、遂に刊行!
認知科学の活況に呼応して、心の科学の哲学的な基礎づけを目指す「認知哲学」。今最も活発なこの分野のなかから基本的なテーマを選び、認知観の変遷を追いながら、認知の本質に迫る。
序論 認知哲学のおもな流れ(信原幸弘)
1 心はコンピュータ──古典主義
2 古典主義への批判
3 心は神経ネットワーク──コネクショニズム
4 心は脳を超えて──環境主義
第一章 心は(どんな)コンピュータなのか──古典的計算主義VS.コネクショニズム(戸田山和久)
1 計算主義とは何か、それは何を問題にしているのか
2 古典的計算主義の認知モデル
3 認知研究の三つのレベル
4 コネクショニズムの認知モデル
5 古典主義者VS.コネクショニスト
6 コネクショニズムと思考の言語
第二章 表象なき認知(中村雅之)
1 表象と計算に伴う問題
2 力学系的認知観
3 力学系の反表象主義
4 折衷論
5 折衷論への批判
6 表象なしでどうやるか
7 結論
第三章 ロボットがフレーム問題に悩まなくなる日(柴田正良)
1 ロボットは苦悩する(あるいはフレーム問題)
2 精確な規則にしたがった記号操作(あるいは古典的計算主義)
3 すべての表象が同時に重なり合って(あるいはコネクショニズム)
4 俺たちは天使じゃない(あるいは自然知性)
第四章 拡張する心──環境─内─存在としての認知活動(染谷昌義)
1 計算の一部は頭の外で行われる
2 認知活動における道具の役割
3 環境操作としての認知活動──認識的行為
4 構造化された環境
5 環境を構造化する道具としての言語──問題変換の集団的達成
6 三つの問題
第五章 存在の具体性──世界内存在と認知(河野哲也)
1 はじめに──世界内存在としての心
2 材質・サイズ・モルフォロジー
3 道具のなかの心
4 心の立脚性
5 巨大な身体としての習慣
6 ユニヴァーサル・デザインの方へ
7 心のカテゴリー
8 心に閉じ込めること、心を閉じ込めること
9 おわりに──存在の具体性
読書案内(信原幸弘)
あとがき
事項索引
人名索引
著者メッセージ
内容説明
基本的なテーマを概観しながら認知の本質に迫る。
目次
序論 認知哲学のおもな流れ
第1章 心は(どんな)コンピュータなのか―古典的計算主義VS.コネクショニズム
第2章 表象なき認知
第3章 ロボットがフレーム問題に悩まなくなる日
第4章 拡張する心―環境‐内‐存在としての認知活動
第5章 存在の具体性―世界内存在と認知
著者等紹介
信原幸弘[ノブハラユキヒロ]
1954年兵庫県生まれ。現職、東京大学大学院総合文化研究科助教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
里馬
スクナ
☆☆☆☆☆☆☆
おたきたお
★
-
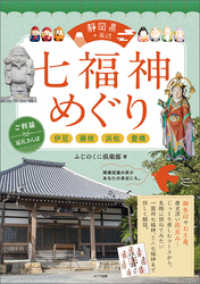
- 電子書籍
- 静岡県+周辺 七福神めぐり ご利益巡礼…
-

- 和書
- 平安宮廷の儀礼文化