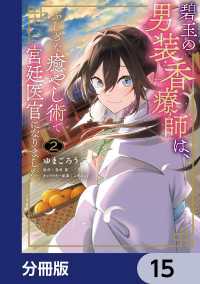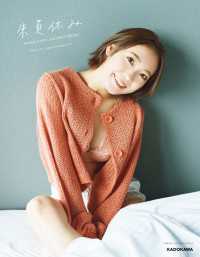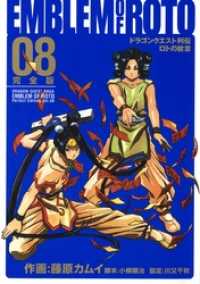出版社内容情報
「社会」とその「コード」、「主体」とその「享楽」―この両者がせめぎ合う場としての詩的言語。
主体が自らを保持してゆくには、社会の中でそのコード(言語)を受け入れ、おのれを合致させてゆかねばならない。一方、主体が社会のコードに身を合わせてゆけば、そこに納まりきらないものが主体から排除される。それが享楽・蕩盡である。このような不合理で不可解な要素をひきうけるのが秘儀であり、詩的テクストなのだ。
本書「第一部」では、哲学(ヘーゲル、フッサール、フレーゲなど)と精神分析(フロイト)を出発点として、テクスト理論
目次
Ⅰ セミオティクとサンボリク
1 言表の現象学的主体
2 コーラ・セミオティク―欲動の秩序づけ
3 フッサールのヒューレとしての意味、判断主体が要求する自然的定立
4 イエルムスレウにおける前提された意味
5 定立的なもの―切断かつ/または境界
6 能記に欠如したものとしての主体をそ措定する鏡と去勢
7 フレーゲによる意味作用―言表と指示作用
8 定立の侵害―「ミメーシス」
9 不安定なサンボリク。サンボリクにおける代替項―フェテシズム
10 意味生成の過程
11 殺人ではない詩について
12 ジェノーテクストとフェノーテクスト
13 四つの意味実践
Ⅱ 否定性―棄却
1 弁証法の四つの「項」
2 ヘーゲルにおける自立的かつ従属的「力」
3 定立的判断を横断する否定性
4 「運動」「気遣い」「欲望」
5 博愛的欲望
6 無矛盾―中立的平和
7 フロイトのいう排斥―棄却
Ⅲ 異質なもの
1 欲動の二分割と他律性
2 疎通、鬱滞および定立的契機
3 「表象体」の相同的体制
4 言語の原理を突き抜けて
5 ヘーゲルとテクストにおける懐疑論とニヒリズム
Ⅳ 実践
1 経験は実践ではない
2 マルクス主義における実践の原子的主体
3 実践における裂け目の喚起―実践的経験
4 転移の言説と区別される実践としてのテクスト
5 弁証法の第二の転倒―経済のあとに続いて、美学
6 『マルドロールの歌』と『ポエジー』。笑い―この実践
7 論理的帰結の蕩盡―『イジチュール』
原注
訳注
邦訳文献一覧
訳者あとがき
用語対照表
索引
内容説明
社会の中における語る主体としての人間のありように正面からたちむかう壮大な企て。社会とコード、主体と享楽―。両者のせめぎあう場としての詩的言語。
目次
1 セミオティクとサンボリク(言表の現象学的主体;フッサルのヒューレとしての意味、判断主体が要求する自然的定立;フレーゲによる意味作用―言表と指示作用;殺人ではない詩について ほか)
2 否定性―棄却(弁証法の第4の「項」;ヘーゲルにおける自立的かつ従属的「力」;フロイトのいう排斥―棄却 ほか)
3 異質なもの(欲動の二分割と他律性;言語の原理を突き抜けて;ヘーゲルとテクストにおける懐疑論とニヒリズム ほか)
4 実践(マルクス主義における実践の原子的主体;弁証法の第二の転倒―経済のあとに続いて、美学;論理的帰結の蕩尽―「イジチュール」 ほか)