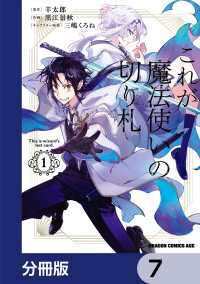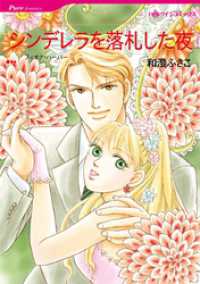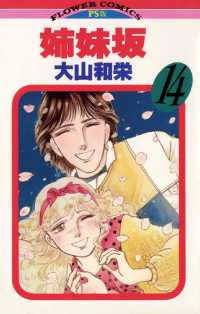出版社内容情報
ホッブスからデイヴィドソンまで.近世以降の主な言語哲学の流れを概観し,自由な解釈を重ねて背後にある問題意識を探る。欧米における言語哲学の標準的な参考書。
〔目次〕
1 戦略
A 観念の全盛期
2 トマス・ホッブスの精神的言説
3 ポール・ロワイヤルの観念
4 バークレー僧正の抽象作用
5 誰の理論でもない意味の理解
B 意味の全盛期
6 ノーム・チョムスキーの生得説
7 バートランド・ラッセルの直知
8 ルートウィヒ・ウィトゲンシュタインの分節化
9 A・J・エイヤーの検証
10 ノーマン・マルコムの夢
C 文の全盛期
11 ポール・ファイヤーアーベントの理解
12 ドナルド・デイヴィドソンの真理
13 言語はなぜ哲学の問題になるのか
付論 開拓地にて―デイヴィドソンの『真理と解釈に関する探究』 について
内容説明
ホッブスカらデイヴィドソンまで。近世以降の主な言語哲学の流れを概観、自由な解釈を重ねて背後にある問題意識を探る。
目次
戦略
トマス・ホッブスの精神的言説
ポール・ロワイヤルの観念
バークレー僧正の抽象作用
誰の理論でもない意味の理論
ノーム・チャムスキーの生得説
バートランド・ラッセルの直知
ルートウィヒ・ウィトゲンシュタインの分節化
A・J・エイヤーの検証
ノーマン・マルコムの夢
ポール・ファイヤーアーベントの理論
ドナルド・ディヴィドソンの真理
言語はなぜ哲学の問題になるのか
付論 開拓地にて―ディヴィドソンの『真理と解釈に関する探究』について
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
魚京童!
24
哲学は言語学に成り下がったのだ。なんかさらっと書いてあったけど、さらっと理解できない。より正確に物事を記載しようとして、理解ができなくなってる。特殊な世界になっちゃった。わかりやすいことをわかりにくくするのが仕事だからね。想像上の問題を扱う際にそれを記述する言語や記号が問題になるのは、他人と共有しないといけないし、共有しないと議論が深まらないからね。でも共有なんてできない。私の三角形は貴方の三角形とは異なる。内角の和が180度でも違うんだよ!2019/06/10
白義
11
英米哲学風のフーコーと言えるハッキングの、言語哲学史。言語の哲学の、観念と精神から意味、公共的な文の検証というパラダイム転換を明晰な知の考古学風の手付きで扱っている。チョムスキーを扱った章が特に見せ場。言語、分析哲学の独創的な史的入門書として使うことも可能。ホッブズやポール・ロワイヤルからデイヴィドソンまで、流れを掴むことが出来る2012/02/01
スミレ雲
3
【図書館本】観念・意味・文、三つの時代の移り変わりをそれぞれの時代の人物を紹介しながら、解説。個人的には、意味の時代が興味があった。ウィトゲンシュタインやラッセル、フレーゲが。意味の時代なのかなと思ったりもするが。2019/12/25
roughfractus02
3
歴史は単称言明(出来事)と純粋存在言明(事象)から成るが、科学言説を扱う分析哲学が前者を後者の具現と考えるのに対し、著者はその逆行である歴史言説を行使し、事象に出来事の時間と場所を与えることで、言語を3つの層または断絶によって画定する。それらは声と気息と沈黙の残響する観念(印刷文字)の18c、指示対象としての意味が問われる(電子的マスメディア)20c前半、アルゴリズムで表現される文(コンピュータ)の20c後半である。こうして、3層は知識というインターフェイスに事象化され、本書のタイトルの問いが可能になる。2017/03/08
袖崎いたる
3
後世への遺産としての公共的な観念の味わい、つまり意義についての研究が言語哲学の中心課題なわけだが、その基礎には知識への反省がある。人文科学は人間を問う。知識は情報とは異なり、誰にも価値と意味を持つ。言語が問題になるのは、その知識が昇華したものであるがゆえ。経験世界の住人は、物理世界を論理世界との相互反映として経験する。彼は原的に論理世界に対してしか影響力を持たない。論理世界とは体系的な知識であり、知識は言語を規定し、言語によって規定されている。それゆえに言語は<世界・実存>の原理を問う哲学の問題になる。…2015/03/08