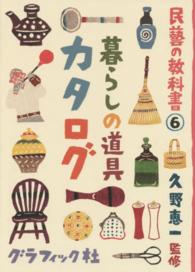出版社内容情報
近年、米銀が開発を手掛け、邦銀においても導入が広がっている代表的信用リスクモデルを徹底比較。
さらにモデルのポートフォリオ適用の実際、オフバランスの信用リスク計測手法から最先端のクレジットデリバティブに至るまで、信用リスク管理の最前線をわかりやすく紹介。
第1章 信用リスクの計測と管理
~新しいアプローチは何故必要なのか
倒産の構造的増加/金融機関よさようなら/より競争的な利鞘/担保価値の低下とのその変動/オフバランス・デリバティブの増加/情報技術革新/BISによるリスクベース必要自己資本規制/付録1.1 個々の銀行勘定に対するリスクベース必要自己資本RBC:Risk-Based Capital)
第2章 信用リスク計測における伝統的アプローチ
エキスパート(専門家による判断)・システム/格付けシステム/信用スコアリング(評点付け)・システム
第3章 オプションとしてのローンとKMVモデル
ローンとオプション特性との関連/KMVクレジット・モニター・モデル/構造モデルと強度基準モデル(lntensity-BasedModel)/付録3.1 Mertonの評価モデル
第4章 VARアプローチ
~JPモリガンのCredit Metricsと関連モデル
バリュー・アリト・リスク(VAR)の概念/Credit Metrics/必要自己資本/技術的な論点と問題/付録4.1 ローン評価におけるフォワード・ゼロ・イールドの算出
第5章 マクロ・シミュレーション・アプローチ
~マッキンゼー・モデルとその他のモデル
循環要因の対処
第6章 リスク中立的評価法
~KPMGのローン分析システム(LAS)とその他のモデル
リスク中立確率の導出/デフォルト確率のリスク中立測度と実際の測度との関係/リスク中立確率と評価/付録6.1 2年からn年に対するリスク中立確率の導出/付録6.2 株式価値からリスク中立確率の導出/付録6.3 期待正味現在価値E(NPV)タイプのアプローチを使ったローン評価
第7章 保険アプローチ
企業消滅モデルとCSFPCredit Risk Plusモデル
企業消滅分析/企業消滅表/CSFP Credit Risk Plus/具体例
第8章 新しい内部モデル・アプローチのまとめと比較
モデル比較/実証シミュレーション
第9章 現代ポートホリオ理論の概要とローン・ポートフォリオへ適用
第10章 ローン・ポートフォリオの選択とリスクの計測
KMVのPortfolioManager/CreditMetrics/付録10.1 単純化された2資産のサブ・ポートフオリオによるN資産ポートフオリオの場合の解決方法
第11章 信用リスクモデルのバックテストとストレステスト
付録11.1 VAR市場リスクモデル:ヒストリカル・シミュレーション・アプローチ
第12章 RAROCモデル
第13章 オフバランス・シートの信用リスクについて
金利スワップの信用リスクとVARの測定/スワップのための信用リスク:BISモデル/付録13.1 BISモデル シミュレーションの各ステップ/付録13.2 スワップ・ポートフオリオのリスクの分散効果
第14章 クレジット・デリバティブ
クレジット・デリバティブとBISの必要自己資本/オプションを用いた信用リスクのヘツジ/スウップによる信用リスクのヘッジ/付録14.1 ピュア・クレジットまたはデフォルト・スワップの価格付けのための現物市場による複製
日本における信用リスク分析の展望
-あとがきにかえて
内容説明
近年、米銀が開発を手掛け、邦銀においても導入が広がっている代表的信用リスクモデルを徹底比較。さらにモデルのポートフォリオ適用の実際、オフバランスシートの信用リスク計測手法から最先端のクレジットデリバティブに至るまで、信用リスク管理の最前線をわかりやすく紹介。
目次
信用リスクの計測と管理―新しいアプローチがなぜ必要なのか
信用リスク計測における伝統的アプローチ
オプションとしてのローンとKMVモデル
VARアプローチ―JPモルガンのCreditMetricsと関連モデル
マクロ・シミュレーション・アプローチ―マッキンゼー・モデルとその他のモデル
リスク中立的評価法‐KPMGのローン分析システム(LAS)とその他のモデル
保険アプローチ―企業消滅モデルとCSFP CreditRiskPlusモデル
新しい内部モデル・アプローチのまとめと比較
現代ポートフォリオ理論の概要とローン・ポートフォリオへの適用
ローン・ポートフォリオの選択とリスクの計測
信用リスクモデルのバックテストとストレステスト
RAROCモデル
オフバランス・シートの信用リスクについて
クレジット・デリバティブ
著者等紹介
サウンダース,アンソニー[サウンダース,アンソニー][Saunders,Anthony]
ニューヨーク大学スターン経営大学院ファイナンス学部長。John M.Schiff Professor of Finance
森平爽一郎[モリダイラソウイチロウ]
学習院大学経済学部卒、青山学院大学大学院経営学研究科修士課程修了、同経済学部助手、86年テキサス大学(オースチン校)経営大学院・ファイナンス学部・博士課程修了、Ph.D。同年より福島大学経済学部助教授、91年より慶応義塾大学総合政策学部助教授。95年より同教授、現在に至る。99年より日本銀行金融研究所客員研究員を兼任。ファイナンス理論、金融工学、保険学(保険、保険数理学)、不動産ファイナンス論を専攻。日本金融・証券計量工学学会副会長(1998‐)、学会誌(英文、和文誌)編集委員、日本ファイナンス学会理事、日本オペレーションズ・リサーチ学会誌編集委員、1992年アメリカリスク・保険学会より最優秀論文賞を受賞
菅原周一[スガワラシュウイチ]
1980年東京工業大学工学部制御工学科を卒業。1989年安田信託銀行入社、DKFTB年金研究所(旧安田年金研究所)資産運用研究部長を経て、2000年10月からみずほ信託銀行資産運用研究所所長。日本証券アナリスト協会カリキュラム委員会委員、慶応義塾大学SFC訪問研究員
鈴木隆之[スズキタカユキ]
1987年に早稲田大学理工学部金属工学科を卒業し同年安田信託銀行(株)入社。投資研究部、リスク統括部、信託開発推進部を経て、2001年5月より営業企画部商品戦略グループ業務推進役。主に新商品開発担当
西岡祐生[ニシオカサチオ]
1995年慶応義塾大学環境情報学部を卒業。同年住友銀行入行(現三井住友銀行)。市場営業第一部を経て、1999年から融資企画部に在職
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。