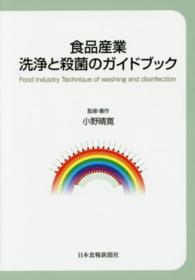出版社内容情報
●内容
白熱電球を発明したのはトーマス・エジソン、蒸気機関を発明したのはジェームス・ワット、飛行機の発明者はライト兄弟と誰でも知っている。しかし、コンピュータを発明したのは誰?と訊かれて、正しく答えられる人はほとんどいない。コンピュータの発明者は、最初に電子的に計算できる機械をつくった人か、あるいは、いわゆるフォン・ノイマン型のコンピュータを最初につくった人か。しかし、その両者とも、これまでのコンピュータの歴史では間違っていた。次の3点は、米国計算機学会が1969年に調査して発表したコンピュータの歴史の一部である。
(1) 最初の電子計算機はENIAC。
(2) プログラム記憶方式はフォン・ノイマンのオリジナルアイデア。
(3) 最初のプログラム記憶方式コンピュータはEDSAC。
現在では、これらはすべて誤りであり、
(i) 最初に電子的に計算ができた計算機はジョン・アタナソフのつくったABCマシン。
(ii) プログラム記憶方式はEDVACの設計チームが考え出したもので、フォン・ノイマン個人ではない。
(iii) 最初のプログラム記憶方式のコンピュータは英国マンチェスター大学のMark-1、通称Baby。
と訂正された。考古学などと違って、資料文献がたくさん残されている20世紀のことであるにもかかわらず、コンピュータの歴史にはこのようにいろいろと間違いがあった。今でも新聞や雑誌にはしばしば、「世界最初のコンピュータENIACは云々」などと、誤った記事が載る。
コンピュータは、今日の高性能を有する形に進歩発達するまで、何人もの天才を必要とした。コンピュータの父とよばれている人が世界中に少なくとも3人いる。英国ではチャールス・バベッジ、ドイツではコンラッド・ツーゼ、米国ではジョン・アタナソフである。本書の目的は、これらの天才達および計算機科学者たちがどうコンピュータを開発してきたかを述べ、いくつもあったコンピュータの歴史の誤りをただすことにある。そして、最初にプログラムというものを考えた人、最初に電子的にデジタルに計算した人、最初のプログラム記憶方式のコンピュータなどと、「最初」にこだわり、歯車の計算機から、いわゆるフォン・ノイマン型のプログラム記憶方式のコンピュータが実用になるまでを述べている。
本書の特色としては、写真を数多く取り入れたことである。90葉もあり、半分以上はカラー写真である。そして、これらの写真の半数近くは、自分が外国に行くたびに大学や博物館に寄って撮りためてきたものである。こういう種類の本にカラー写真をたくさん載せるのは手間やらコストやらが大変なのであるが、敢えて挑戦してみた。読んで、見て楽しめる本にしたかった。
もうひとつの本書の特色は、索引である。かねてから、どの本の索引にも不満をもっていた。不十分だったり間違いがあったりして、なかなか索引から必要な本文記事にたどりつけなかったからである。そこで本書では、自前で索引作成用のプログラムをつくり、抜け落ちや間違いがないようコンピュータを使って原稿から直接、索引を作成した。見た目にはとくに変りはないが、こういった本の索引作成のサンプルのつもりである。(「はじめに」より)
●目次
第1章 計算の道具
1.1 アバカス、そろばん
1.2 乗算用の算木、ネピアの骨
第2章 歯車を使った計算機
2.1 レオナルド・ダ・ビンチの計算機械
2.2 シッカートの計算機
2.2.1 乗算部
2.2.2 加減算部
2.2.3 メモリ
2.2.4 シッカートの計算機完成350周年記念式典
2.3 パスカリーヌ
2.4 ライプニッツの計算機
2.5 その他の歯車計算機
第3章 階差機関と解析機関
3.1 数表の危機
3.2 第1階差機関
3.3 階差機関の7分の1のモデル
3.4 シュウツ親子の階差機関
3.5 階差機関未完の理由
3.6 第2階差機関
3.7 バベッジの生誕200年記念行事と第2階差機関の複製
3.8 解析機関
3.9 チャールズ・バベッジ
3.10 エイダ
3.11 ジャカールとジャカード織機
3.12 バベッジの先見性
第4章 最初のプログラマブル計算機Z1、Z3
4.1 個人が独力でつくった計算機
4.2 Z1
4.3 Z2
4.4 Z3
4.5 Z4
4.6 2進浮動小数点表現
4.7 プランカルキュール
4.8 Z1とZ3の復元
4.9 コンラッド・ツーゼ
第5章 最初に電子的にデジタルに計算したABCマシン
5.1 ABCマシン
5.2 特許取得せず
5.3 ABCマシンの復元
5.4 ジョン・アタナソフ
5.5 クリフォード・ベリー
第6章 電子式暗号解読機コロッサス
6.1 エニグマとその解読
6.2 ボンブとコロッサス
6.3 コロッサスの復元
6.4 アラン・チューリング
6.5 チューリング賞
第7章 最初のプログラマブル実用計算機ASCCハーバード・マーク1
7.1 ASCC
7.2 ハーバード・マーク1
7.3 ホワード・エイケン
7.4 グレース・ホッパー
第8章 最初に実用になった電子計算機ENIAC
8.1 弾道表作製計算機
8.2 ENIACの構成
8.3 ENIACの完成
8.4 ENIACの安定性
8.5 ENIACの評価
8.6 ワンチップENIAC
8.7 モークリとエッカート
8.7.1 モークリ
8.7.2 エッカート
8.7.3 モークリとエッカートの出会い
8.7.4 1952年の米国大統領選挙
8.7.5 エッカート・モークリ賞
第9章 最初のプログラム記憶方式コンピュータ
9.1 SSEM、Baby
9.2 Manchester Mark1とFerranti Mark1
9.3 最初のプログラム
9.4 Babyの復元
9.5 ウィリアムズとキルバーン
第10章 最初に実用になった近代的コンピュータEDSAC
10.1 EDSAC
10.2 イニシャル・オーダー
10.3 EDSAC2
10.4 EDSAC99とソフトウエア・シミュレータ
10.5 EDSACと日本のコンピュータ
10.6 モーリス・ウィルクス
第11章 最初にプログラム記憶方式を取り入れたコンピュータEDVAC
11.1 EDVACの構想
11.2 EDVACの構成
11.3 EDVACの完成と運用
11.4 ムーア校の夏季講習会
第12章 ENIAC裁判
第13章 フォン・ノイマン型論争
13.1 フォン・ノイマン型はフォン・ノイマンのオリジナルアイデアか
13.2 フォン・ノイマン
第14章 おわりに
14.1 計算機の歴史の誤り
14.2 結局コンピュータを発明したのは誰か
目次
計算の道具
歯車を使った計算機
階差機関と解析機関
最初のプログラマブル計算機Z1、Z3
最初に電子的にデジタルに計算したABCマシン
電子式暗号解読機コロッサス
最初のプログラマブル実用計算機ASCCハーバード・マーク1
最初に実用になった電子計算機ENIAC
最初のプログラム記憶方式コンピュータ
最初に実用になった近代的コンピュータEDSAC
ENIAC裁判
フォン・ノイマン型論争
おわりに
著者等紹介
大駒誠一[オオコマセイイチ]
1959年慶應義塾大学工学部計測工学科卒業。1959~1964年小野田セメント株式会社。1964~2001年慶應義塾大学理工学部管理工学科。2001~2005年東北公益文科大学公益学部公益学科。2001年慶應義塾大学名誉教授。工学博士(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ドリアン・グレイ
周藝傑
しょうじ