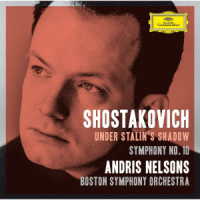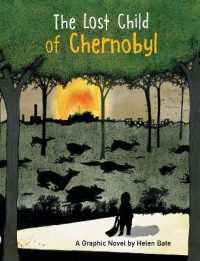出版社内容情報
紀元前3800年ごろ,メソポタミア南部に世界最古の都市文明を築いたシュメールの人々は,当時の思考や事跡などを粘土板に刻み残した。現代にも膨大に残されている粘土板に純粋な”数学文書”は極僅かしか存在しないが,行政や経済に関する文書には当時の数学的知識の様子を窺わせるものが多く存在する。この書籍は,それら粘土板を紐解くことで数学の源流に迫ろうという,世界初のシュメール数学に関する概説書である。
最初に,自然数・分数と小数・四則演算といった現代生活に於いても欠かすことのできない知識の起源を解説する。後半では,時間や角度と,それらにみられる60進法,方円の面積計算や円周率の起源のほか,約4600年前の人類が複利計算を行っていた可能性を示唆する粘土板を紹介する。粘土板一つひとつについて計算過程・思考過程を省略せず提示し,古代文明の息吹が感じられるよう丁寧に解説した。
内容説明
自然科学の各分野におけるスペシャリストがコーディネーターとなり、「面白い」「重要」「役立つ」「知識が深まる」「最先端」をキーワードにテーマを選びました。第一線で研究に携わる著者が、自身の研究内容も交えつつ、それぞれのテーマを面白く、正確に、専門知識がなくとも読み進められるようにわかりやすく解説します。
目次
1 数学の痕跡を探す
2 自然数と分数
3 割り算と数表
4 面積と体積の計算
5 エンメテナ碑文中の複利計算
6 角度の起源
7 台形の二等分線の長さ
8 巨大な数への関心
9 バビロニアの数学への影響
著者等紹介
室井和男[ムロイカズオ]
1954年栃木県生まれ。1978年東北大学理学部物理学科卒業。仙台市内の予備校で数学講師として31年間教壇に立ったのち、2009年退職。現在は、古代の数学文化の解明を主な分野として研究に専念している。著書『バビロニアの数学』東京大学出版会、2000。(2010年度日本数学会賞出版賞受賞)ほか
中村滋[ナカムラシゲル]
1943年埼玉県生まれ。1965年東京大学理学部数学科卒業。1967年東京大学大学院理学系研究科修士課程修了、理学修士。東京商船大学商船学部教授などを経て、東京海洋大学名誉教授、日本フィボナッチ協会副代表。専門は数論(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Koning
トムトム
タカオ
ソルト佐藤
ほにょこ