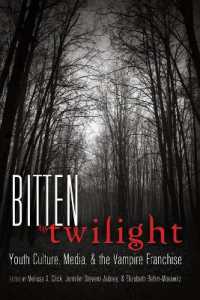目次
1時間目 光が生む不思議な現象(光は折れ曲がる!;はね返る光のおかげで物が見える;飛び散る光、重なる光―散乱と干渉)
2時間目 光と色の三原色(3色の組み合わせで、色が決まる)
3時間目 光の正体を求めて(光の速さの探究;光の正体は、波でもあり粒子でもある)
4時間目 常識をくつがえした光速度不変の原理(光の速さは常に変わらない;超光速は実現不可能?)
著者等紹介
吉田直紀[ヨシダナオキ]
東京大学大学院理学系研究科教授。Ph.D.。1973年、千葉県生まれ。マックスプランク宇宙物理学研究所博士課程修了。専門は宇宙物理学。主な研究テーマは、観測的宇宙論と宇宙物理学。とくに大規模構造数値シミュレーションを用いた星、銀河、ブラックホールの形成についての研究を行っている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
おたま
27
今回は比較的身近な光の様々な現象(屈折、反射、散乱、干渉)、光の三原色等について書かれていて分かりやかった。光が粒子か波かという聞きなれた問題から、さらに光速度の不変性→特殊相対性理論という展開で、これまでこのシリーズでも扱ってきたことがらなので、理解できないことはほぼなかった。それだけに少しものたりない感じももった。シリーズ名が「文系のためのめっちゃやさしい」から「文系のための東大の先生が教える」にいつのまにか変わっていたが、何か深い意図があるんだろうか? もとのままでいいと思うけどなあ。2023/09/27
GELC
11
仕事で照明を扱うことがあるので、光学系の設計の基礎を振り返る意味で手に取った。前半の屈折・反射・散乱などの身近で観察できる光の性質、色の原理などは、良い復習になったが、ここまでわかりやすく解説した本は初めて! 本当にわかりやすく、教科書にもここまで書いてくれるか、副読本に採用するかして欲しいぐらい。後半の光の正体、光速の章もやや難しいが、初めて相対性理論の触りが理解できて、この世の成り立ちに思いを馳せることができた。本当にタイトル通り、光って不思議だ。。。2023/11/26
K
1
(2023,425)「めちゃくちゃやさしく解説」ってあるけど、私には、わからないことばっかり。基礎知識、読解力必須の本。そもそも、私が、受験勉強でなくて、光によって(と思われる)現象の不思議を知りたい(この本は手段本)だから?粒とか波とか速さとか、わかればいいのかと思ったけれど、意味わからない。かろうじて、昼の青空と夕方の夕焼けが、大気中のチリに当たって散乱するのは距離の違いというのはわかったけど、なんで二色刷りなのよ?p86とp89の絵、考えて読まないとわからないよ。海の青の解説はない。期待してたのにな2024/09/26
dahatake
1
電磁波でもあり、粒子でもある、光の性質の教養部分を一通り知る事が出来る。絵が大きくて相変わらず読みやすい。 素粒子力学の話が最後にやっぱり出てくるので。そっちも押さえておきたいモノ。2024/06/30
-
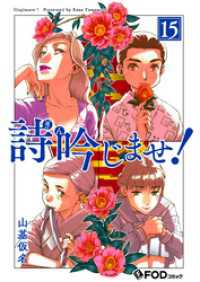
- 電子書籍
- 詩吟じませ! 15 FOD
-

- 電子書籍
- 新特命係長 只野仁(分冊版) 【第13…