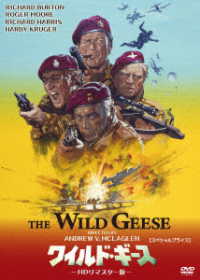出版社内容情報
※【試し読み】はこちら(PDF)
【紀伊國屋書店チャンネル】
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
【精神科医・松本俊彦氏 推薦!】
(『誰がために医師はいる――クスリとヒトの現代論』著者)
「殴ってもわからない奴はもっと強く殴ればよい?――まさか。
それは叱る側が抱える心の病、〈叱る依存〉だ。
なぜ厳罰政策が再犯率を高めるのか、
なぜ『ダメ。ゼッタイ。』がダメなのか、
本書を読めばその理由がよくわかる」
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
叱らずにいられないのにはわけがある。
「叱る」には依存性があり、エスカレートしていく――その理由は、脳の「報酬系回路」にあった!
児童虐待、体罰、DV、パワハラ、理不尽な校則、加熱するバッシング報道……。
人は「叱りたい」欲求とどう向き合えばいいのか?
●きつく叱られた経験がないと打たれ弱くなる
●理不尽を我慢することで忍耐強くなる
●苦しまないと、人は成長しない……そう思っている人は要注意。
「叱る」には効果がないってホント?
子ども、生徒、部下など、誰かを育てる立場にいる人は必読!
つい叱っては反省し、でもまた叱ってしまうと悩む、あなたへの処方箋。
【目次】
はじめに
Part 1 「叱る」とはなにか
1 なぜ人は「叱る」のか?
2 「叱る」の科学――内側のメカニズムに目を向ける
Part 2 「叱る」に依存する
3 叱らずにいられなくなる人たち
4 「叱らずにいられない」は依存症に似ている
5 虐待・DV・ハラスメントとのあいだにある低くて薄い壁
Part 3 〈叱る依存〉は社会の病
6 なぜ厳罰主義は根強く支持されるのか?
7 「理不尽に耐える」は美徳なのか?
8 過ちからの立ち直りが許されないのはなぜか?
Part 4 〈叱る依存〉におちいらないために
9 「叱る」を手放す
あとがき/〈叱る依存〉をより深く考えるためのブックリスト/注
【著者】村中直人(むらなか・なおと)
1977年生まれ。臨床心理士・公認心理師。一般社団法人子ども・青少年育成支援協会代表理事。Neurodiversity at Work株式会社代表取締役。人の神経学的な多様性に着目し、脳・神経由来の異文化相互理解の促進、および学びかた、働きかたの多様性が尊重される社会の実現を目指して活動。2008年から多様なニーズのある子どもたちが学び方を学ぶための学習支援事業「あすはな先生」の立ち上げと運営に携わり、現在は「発達障害サポーター’sスクール」での支援者育成にも力を入れている。著書に『ニューロダイバーシティの教科書――多様性尊重社会へのキーワード』(金子書房)がある。
内容説明
「叱る」には依存性があり、エスカレートしていく―その理由は、脳の「報酬系回路」にあった!児童虐待、DV、パワハラ、加熱するバッシング報道…。人は「叱りたい」欲求とどう向き合えばいいのか?つい叱っては反省し、でもまた叱ってしまうと悩む、あなたへの処方箋。
目次
1 「叱る」とはなにか(なぜ人は「叱る」のか?;「叱る」の科学―内側のメカニズムに目を向ける)
2 「叱る」に依存する(叱らずにいられなくなる人たち;「叱らずにいられない」は依存症に似ている;虐待・DV・ハラスメントとのあいだにある低くて薄い壁)
3 “叱る依存”は社会の病(なぜ厳罰主義は根強く支持されるのか?;「理不尽に耐える」は美徳なのか?;過ちからの立ち直りが許されないのはなぜか?)
4 “叱る依存”におちいらないために(「叱る」を手放す)
著者等紹介
村中直人[ムラナカナオト]
1977年生まれ。臨床心理士・公認心理師。一般社団法人子ども・青少年育成支援協会代表理事。Neurodiversity at Work株式会社代表取締役。2008年から支援事業「あすはな先生」の立ち上げと運営に携わり、現在は「発達障害サポーター’sスクール」での支援者育成にも力を入れている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
のっち♬
168
臨床心理士が示唆する〈叱る依存〉が齎す双方への逆効果。利他的にも利己的にも活性化する報酬系回路、馴化や回避によるスパイラル機序、効果的限界、対処法を眺める分には良い。しかし、叱られる側ばかり扱う人のマクロ視点や叱責の概念自体に曲解があるようで、「叱る」から「虐待」を繋げるのは度を越した拡大解釈だと思う。推論の蓄積を次第に断定に発展させるデータ引用や考察も持論ありきな印象。例えば、日本の医療事情が絡んだ経口避妊薬承認問題、楯にもできる少年法などを安易に叱る依存と結びつける思考には専門分野への依存が見られる。2023/05/07
ehirano1
157
約10年程前に「叱る技術」なる書籍を以て「叱る」について勉強したつもりでいましたが、時は経ち、もはや「叱る」こと自体がよろしくないようです。具体的には、「叱る」ことは思ったほど成長や学びに繋がらないとのことで、その理由は『叱られてネガティヴになると、ヒトの思考力は低下するから』とのこと。但し、相手の行動をストップさせるには有効とのこと。2024/10/22
せ~や
128
面白かったです!「叱る」という行為を、脳神経学+心理的な視点から説明していて、「叱る」が生む効果もですが、「叱る人」「叱られる人」にもたらす効果も説明されていて、すごくわかりやすくて読みやすかったです。「叱る」はすでに上下関係があって、叱る側の欲や何かを満たすためのモノで、「あなたを思って」って言葉は叱る側の言い訳だって思ってたし、「叱る」を極力しないようにと思ってましたが…ちょっと答えが見つかりました。きちんと考えて、「叱る」をしないといけないと感じました。☆5.02022/05/19
R
92
本当か?と思いつつ読んだのだけども、DVの仕組みが、とても整然と説明できてしまうので、深く納得させられた。叱るという行為に依存性があって、叱ることで人より偉いと錯覚できるある種の快楽報酬を得るために安易に叱る行為に走ってしまうというのが、SNSとかの正義を振りかざすそれにも適用されるというのはなるほどと思った。叱るというアクションに対して、思った通りの反省を引き出せないとエスカレートしてしまうのも、納得できてしまうんだが、叱られる方も耐性だけでなく依存が現れるというのが恐怖だわ。2023/02/02
ちゅんさん
57
これは読んでよかった。“学びや成長を促進するという意味での「上手な叱り方」は存在しません”この一言につきる。自分は怒ると叱るを区別出来てるから大丈夫、と思ってたけど全然そんなことはなく相手にネガティブな感情を与えて変化を促すこと自体が良くない。すごく学びになった。説教しながら恍惚としているあいつに読ませたい2023/03/09
-

- 電子書籍
- 聖ガーディアン【分冊版】 1 カドカワ…
-

- 和書
- 私語と 河出文庫