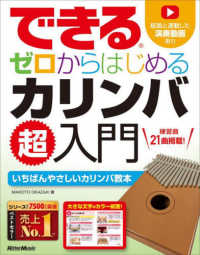出版社内容情報
繁栄のきわみにあった大英帝国首都に巣食う不条理とやがて「ゆりかごから墓場まで」と呼ばれる福祉制度が萌芽するまでをつぶさに描く19世紀末、繁栄のきわみにあった大英帝国の首都に
すさまじい貧困のなか6000人が暮らすスラムがあった――
都市型スラムの原型ともいわれるイースト・エンドのニコル地区は
いかに生まれ、消えていったのか
社会主義や優生学など当時生まれた思想はいかなる影響を与えたのか
福祉制度の成立にいかに寄与したのか――その歴史に迫る
「徹底的にリサーチされた、傑出した社会史。対象に向けた視線が優しい」(インディペンデント紙)
「聡明な歴史家サラ・ワイズが手がけた本書は、ヴィクトリア期の悲惨を描いた表面的なメロドラマにはならない……ここには本物の人生が描かれている。表立って語られずとも、読者は今の時代に通じるものについて考えないではいられない」(デイリー・テレグラフ紙)
「ニコルは今日における都市型スラムの原型であった。本書を読んで、驚愕せよ」(ニュー・ステイツマン誌)
サラ・ワイズ[ワイズ サラ]
著・文・その他
栗原 泉[クリハラ イズミ]
翻訳
内容説明
都市型スラムの原型ともいわれるイースト・エンドのニコル地区はいかに生まれ、消えていったのか。社会主義や優生学など当時生まれた思想はいかなる影響を与えたのか。福祉制度の成立にいかに寄与したのか―その歴史に迫る。
目次
第1部 空文(飢餓帝国―オールド・ニコル一八八七年;スラムはこうして生まれた ほか)
第2部 スラムに生きる(プリンス・アーサー;助けの手 ほか)
第3部 対策(象を突っつく―社会主義とアナーキズム;声を上げる―露店・予防接種・義務教育 ほか)
第4部 ストライプランド(夢見る人たち―ロンドンの行政改革;バウンダリー・ストリート計画―交錯する思惑)
著者等紹介
ワイズ,サラ[ワイズ,サラ] [Wise,Sarah]
バークベック・カレッジで、ヴィクトリア期を研究し、修士号を取得。現在はカリフォルニア大学ロンドン研究センターで19世紀英国の社会史を教えるほか、「TLS」「ヒストリー・トゥデイ」「BBCヒストリー・マガジン」「フィナンシャル・タイムズ」などに、ロンドンの都市と労働者の歴史、医学史、心理地理学について寄稿している
栗原泉[クリハライズミ]
翻訳家(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
BLACK無糖好き
爺
hal
kuukazoo
qoop