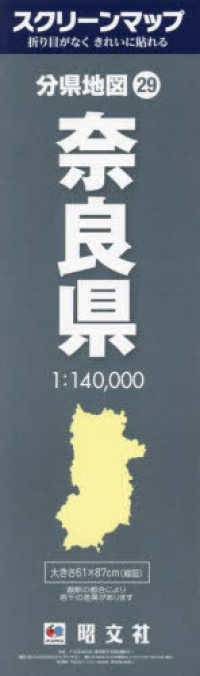出版社内容情報
アルツハイマー型に次いで多いとされるレビー小体型認知症とは、どのような病気か。在宅・医療・介護現場で起こる現状と課題に迫る。
幻視、転倒、高齢者のうつ、大きな寝言…… もしかしてレビー小体型?!
アルツハイマーの次に多い認知症、その数64万人! もう知らないではすまされない――
「床に蛇が這っている」「同じ顔をした妻が2人いる」「家が傾いて見える」「夫を見知らぬ侵入者と思い込んで通報する」……
レビー小体型認知症は、精神科医である著者が1976年に最初に発見した病気で、近年認知症・介護分野におけるホットなトピックとして注目を集めている。日本で64 万人と言われる患者数に比して、メディアでの報道や書籍などの情報は少なく、一般に知られているとはいえない。医師でさえ正しい知識を持つ人が少ないために、何年もの間正しい診断と治療を受けられず、「幻視」などの特異な症状に苦しみつづける人が多いという現状がある。
レビー小体型認知症は、正しい診断と適切な処方によって、症状を軽減させたり、その後の病気の進行を遅らせることもできるため、早期発見・早期治療がその後を大きく左右する病気でもある。
本書は、この病気について広く知っていただくために刊行された。第一人者による病気の平易な解説とともに、家族の体験談なども織り交ぜ、現在医療・介護現場などで起こっている問題やこれからの課題に迫っている。
part1認知症という病気
1 認知症をめぐるプロローグ
痴呆から認知症へ
「認知症大国」日本
2 認知症とは
認知症は病気である
認知症にはさまざまな種類がある
アルツハイマー型認知症とは
アルツハイマー型認知症特有のもの忘れ
その他の認知障害
アルツハイマー型認知症の犯人説
BPSDとよばれる言動
脳血管性認知症は生活習慣病に起因
状況にそぐわない言動が目立つ前頭側頭型認知症
治る認知症も
認知症は若い人にも起こる
3 認知症医療と介護の今
早期発見・診断がますます重要に
介護の新しいカタチ
part2レビー小体型認知症を知っていますか?
1 パーキンソン病とは
パーキンソン病の発見は200年前
さまざまな運動症状を示すパーキンソン病
運動系以外にも症状が
パーキンソン病の診断と治療
ーキンソン病と認知症
2 レビー小体型認知症とは
レビー小体型認知症とは
筆者による発見を端緒に
3 さまざまな症状
幻視――そこにないものがはっきり見える
幻視はなぜ起こる?
幻視は妄想に発展することも
その他にもさまざまな視覚認知障害が
パーキンソン症状――筋肉が硬くなる、転びやすい
認知障害――初期には比較的軽い
認知の変動――よいときと悪いときの波がある
レム睡眠行動障害――夜中の大きな寝言・異常行動
夜間せん妄とレム睡眠行動障害
過眠――日中のひどい眠気
うつ――レビー小体型認知症を疑え
自律神経症状――さまざまな症状で現れる
起立性低血圧には要注意
排泄にまつわる自律神経症状
汗を大量にかく、汗をかかない
薬に対する過敏性
4 原因とされるレビー小体
レビー小体とレビー小体病
αシヌクレインの解明がカギ
2種類のレビー小体型認知症
発病はいつか?
part3 レビー小体型認知症の診断と治療
1 診断の方法
問診と心理検査
後頭葉に血流の低下
心臓を見れば診断できる!?
レビー小体型認知症の診断基準
誤診されている人が多い
2 レビー小体型認知症に対する治療
レビー小体型認知症に用いられる薬
認知症薬「アリセプト」
アリセプトとレビー小体型認知症
漢方薬「抑肝散」の効果
抗精神病薬には注意
パーキンソン症状には抗パーキンソン病薬
抗パーキンソン病薬を使う難しさ
脳に刺激を与える治療法
抗うつ薬は慎重に
新たに加わった認知症薬
part4 レビー小体型認知症をかかえて生きる人たち
レビー小体型認知症の典型例
Yさんのケース
「純粋型」の女性の例
誤診から正しい診断・治療へ
当事者の体験談から
part5 レビー小体型認知症、その介護と生活の工夫
1 病院・医師を見つける
病院・医師選びが大事
医師と上手に付き合うために
2 介護の方法と対応の仕方
罹病機関はアルツハイマー型よりも短い
病気とストレス
幻視への基本的な態度
幻視が現れたときは……
幻視との“付き合い方”
問題にならない思い込み、問題になる妄想
認知障害と認知の変動への対応
転倒に気をつける
認知障害と転倒
起立性低血圧を予防する
薬の影響をよく観察
終末期と胃ろう
3 相談機関や制度・サービスを利用する
家族をサポートする「支える会」
難病の認定は可能か
介護保険サービスを利用する
在宅介護を上手に続けるために
いい施設を選ぶには
part6 レビー小体型認知症をめぐる課題
潜在者が大多数を占める
医師を増やせ
アリセプトに保険適応を
コラム
マイケル・J・フォックス 他
【著者紹介】
小阪憲司:精神科医。1939年、三重県生まれ。金沢大学医学部卒業。名古屋大学医学部精神医学教室講師、横浜市立大学医学部精神医学講座教授、聖マリアンナ医学研究所所長、横浜ほうゆう病院院長などを経て、現在、メディカルケアコート・クリニック院長。1976年以降の一連の研究にて、世界で初めてレビー小体型認知症について明らかにした。横浜市立大学名誉教授、レビー小体型認知症研究会代表世話人、レビー小体型認知症家族を支える会顧問、若年認知症研究会代表世話人などを務める。著書に『認知症はここまで治る・防げる』[主婦と生活社]、『知っていますか? レビー小体型認知症』、『レビー小体型認知症の介護がわかるガイドブック』(共著)、『「パーキンソン病」「レビー小体型認知症」がわかるQAブック』(共著)[以上、メディカ出版]、『レビー小体型認知症の臨床』[共著、医学書院]、『認知症の防ぎ方と介護のコツ』[角川マーケティング]、『プライマリケア医の認知症診療入門セミナー』[新興医学出版社]などがある。
尾崎純郎(執筆協力):株式会社harunosora代表取締役・編集長、レビー小体型認知症家族を支える会顧問。中央法規出版株式会社、株式会社メディカ出版を経て、現職。これまで約20年にわたって、介護や認知症分野の編集者として、数々の単行本・雑誌を手掛けてきた。2004年には、認知症ケア専門誌「りんくる」を創刊し、編集長を務めた。他に、日本老年行動科学会常任理事。
内容説明
あなたは「レビー小体型認知症」を知っていますか?幻視、転倒、大きな寝言、立ちくらみ…。アルツハイマー型とはこんなに違う。
目次
1 認知症という病気
2 レビー小体型認知症を知っていますか?
3 レビー小体型認知症の診断と治療
4 レビー小体型認知症かかえて生きる人たち
5 レビー小体型認知症、その介護と生活の工夫
6 レビー小体型認知症をめぐる課題
著者等紹介
小阪憲司[コサカケンジ]
精神科医。1939年、三重県生まれ。金沢大学医学部卒業。名古屋大学医学部精神医学教室講師、横浜市立大学医学部精神医学講座教授、聖マリアンナ医学研究所所長、横浜ほうゆう病院院長などを経て、メディカルケアコートクリニック院長。1976年以降の一連の研究にて、世界で初めてレビー小体型認知症について明らかにした。横浜市立大学名誉教授、レビー小体型認知症研究会代表世話人、レビー小体型認知症家族を支える会顧問、若年認知症研究会代表世話人などを務める
尾崎純郎[オザキジュンロウ]
株式会社harunosora代表取締役・編集長、レビー小体型認知症家族を支える会顧問。中央法規出版株式会社、株式会社メディカ出版を経て、現職。これまで約20年にわたって、介護や認知症分野の編集者として、数々の単行本・雑誌を手掛けてきた。2004年には、認知症ケア専門誌「りんくる」を創刊し、編集長を務めた。他に、日本老年行動科学会常任理事(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
森博嗣作品が好き
こんころ
A.Sakurai
mami
Honesty
-

- 電子書籍
- 悪女皇后の専属侍女【タテヨミ】第109…
-
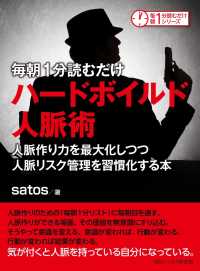
- 電子書籍
- 毎朝1分読むだけハードボイルド人脈術。…