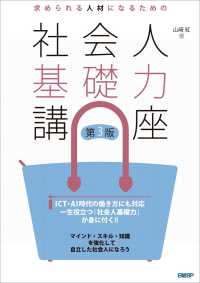出版社内容情報
いじめ、不登校・ひきこもり、反抗期、性的逸脱、ドラッグ、うつ病、摂食障害――思春期の問題行動や心の病には「自尊心」の低さがひそんでいる。人気精神科医が教える、「自尊心」と「コミュニケーション力」の高い子どもの育て方。
■思春期のうつ病は、大人と同じくらい多い?
■「虐待」と「しつけ」の境界線は?
■禁欲教育はかえって中絶率を高める?
■薬物に手を出す子に「いい子」が多い理由は?
■親の離婚が子どもの成長に悪影響を及ぼさない条件とは?
■「空気を読む」ばかりでは自尊心は育たない?
■子どもの危機を救う一言とは?
うつ病等への治療効果が実証されている対人関係療法の第一人者であり、思春期前後の心の問題を専門にする著者は、10代に多い心の病や問題行動の奥底には、「自尊心」と「コミュニケーション力」の低さが潜んでいると言う。
本書では、自分を大切にする気持ちである「自尊心」と、心の健康を決める「コミュニケーション力」の2つを育てるために必要な知識と心がまえを、大人のどのような対応が自尊心を育て、逆にどのような態度が自尊心を損なうのかという具体例とともに、やさしく説いている。思春期の子をもつ親や教育関係者には必読の一冊。
1.思春期の意味
思春期とは/大人になるために必要なプロセス
2.人間の性格の成り立ち
生まれつき決まっている4つの因子/「長所」と「短所」を分けるもの/後天的に作られる3つの因子/変えられない「性格」を受け入れる
3.思春期のゆらぎと自尊心
自尊心が低下すると/自尊心の重要性
4.自尊心を高める子育て
子どもの存在そのものを肯定する/まずほめてから注意する
5.反抗期の子どもとの接し方
子どもの「現在」を否定しない/非暴力コミュニケーション
6.親の不安と過保護
「過保護」と「いい子」は要注意/親の不安をコントロールする
7.感情の扱い方を学ぶ
ネガティブな感情を否定しない/すべての「感情」は正しい
8.不安の上手な扱い方
「解決すべき不安」と「感じるしかない不安」/不安な時期には無理をしない
9.コミュニケーション力は一生の財産
問題行動の背景にあるもの/「キレる」子どもたち
10.大人のコミュニケーションから見直す
言いにくい内容の伝え方/自分の言いたいことが伝わったと思い込まない/相手の言ったことを理解したと思い込まない
11.コミュニケーションを断たないためのコツ
押しつけないコミュニケーションとは/アドバイスをしない
12.自分の「気持ち」を話す
「評価」ではなく「気持ち」を話す/「気持ち」を話すことの力
13.しつけのコツは「一貫性」
子どもにとって安全な環境とは/キレる子どもへの対応
14.大人の「ものさし」が歪むとき
子どもを救う一言/「よい厳しさ」とは
15.「子どもから学ぶ」という姿勢
間違いを認められない親/時には大人も「生徒役」になる
16.思春期の問題行動を「医学モデル」で考える
見過ごされがちな思春期のうつ病/病気の人の義務/摂食障害と万引き
17.思春期のうつ病
うつ病とはなにか/うつ病の症状/思春期うつ病の特徴/思春期うつ病の治療/「双極性障害」の可能性
18.対人関係ストレスへの対処
自分が相手に期待していること/相手が自分に期待していること/期待の「ずれ」を調整する
19.役割が変化するとき
支えてくれる人たちの存在/悲哀のプロセス/変化に伴う感情を受け入れる
20.親の離婚の影響
両親の不仲を離婚後に持ち越さない/子どもとしての時間を与える/親自身の心のケア
21.思春期の拒食症
ペースの違いを「役割期待のずれ」として見る/思春期という「役割の変化」
22.「母親の育て方」のせい?
子どもの現在を見る/モンスターペアレント
23.自分がどう見られるか」にとらわれる病気
摂食障害・身体醜形障害・社交不安障害/ありのままの自分を表現して受け入れてもらっていない
24.「自分の問題」と「他人の問題」を区別する
親の「境界線」問題/顔色を読まなければならない親
25.家族にしかできないこと
とにかく話を聴く/どんな気持ちも受け止める
26.話しやすい環境づくり
評価を下さない態度/子どもと一緒に活動する
27.悩みを打ち明けられたら
「決めつけ」を手放す効果/思ったように受け止めてもらえない場合
28.「待つ」ことと「感謝する」こと
子どもの成長を信じる/「できるようになったこと」に注目する
29.いじめにどう向きあうか
「修復的司法」という手法/いじめを解決するコミュニケーション
30.「ひきこもり」とコミュニケーション
「ひきこもり」を隠す親/コミュニケーションへの信頼感を育てる
31.思春期の「性」
正しい知識を与える/自尊心と「性」
32.問題行動への対応――「共感」と「教育」のバランス
「気持ち」に共感する/「気持ち」を利用して事態を変える
33.自分の限界を知る
「現在」に生きることの重要性/大きな流れの中に今の自分を位置づける
34.それぞれの人がベストを尽くしている
親が罪悪感を手放す/子どもも常にベストを尽くしている
【著者からのコメント】
10代の子どもと関わる上で最も大切なことは、実は非常にシンプルだと私は思っています。今まで多くの患者さんを治療する中で実感してきたことですが、ポイントとなるのは、「自尊心」と「コミュニケーション力」です。「自尊心」というのは、自分の存在を肯定する気持ちです。心の病になる子どもも、非行や犯罪に走ってしまう子どもも、「自尊心」に問題を抱えていることがほとんどです。人間は自分の存在を肯定できて初めて前向きに生きていくことができますし、社会とも折りあっていこうと思えるものだからです。自尊心が高い子どもは、自分も他人も大切にすることができるのです。 「はじめに」より
【著者紹介】
1968年東京生まれ。慶應義塾大学医学部卒、同大学院修了(医学博士)。現在、対人関係療法専門クリニック院長、慶應義塾大学医学部非常勤講師(精神神経科)。摂食障害をはじめとする思春期前後の問題や家族の病理が専門。2000年6月~2005年8月、衆議院議員として児童虐待防止法の抜本改正などに取り組む。うつ病等への治療効果が実証されている「対人関係療法」の日本における第一人者。主な著書に、『怖れを手放す アティテューディナル・ヒーリング入門ワークショップ』(星和書店)、『自分でできる対人関係療法』『対人関係療法でなおす うつ病』(以上、創元社)、『拒食症・過食症を対人関係療法で治す』(紀伊國屋書店)など多数。
内容説明
いじめ、不登校・ひきこもり、反抗期、性的逸脱、ドラッグ、うつ病、摂食障害―思春期の問題行動や心の病には、「自尊心」の低さがひそんでいる。人気精神科医が教える、「自尊心」と「コミュニケーション力」の高い子どもの育て方。
目次
思春期の意味
人間の性格の成り立ち
思春期のゆらぎと自尊心
自尊心を高める子育て
反抗期の子どもとの接し方
親の不安と過保護
感情の扱い方を学ぶ
不安の上手な扱い方
コミュニケーション力は一生の財産
大人のコミュニケーションから見直す〔ほか〕
著者等紹介
水島広子[ミズシマヒロコ]
1968年東京生まれ。慶應義塾大学医学部卒、同大学院修了(医学博士)。現在、対人関係療法専門クリニック院長、慶應義塾大学医学部非常勤講師(精神神経科)。摂食障害をはじめとする思春期前後の問題や家族の病理が専門。2000年6月~2005年8月、衆議院議員として児童虐待防止法の抜本改正などに取り組む。うつ病等への治療効果が実証されている「対人関係療法」の日本における第一人者(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
クリママ
しゅわ
たまきら
ヨル
あんみつ