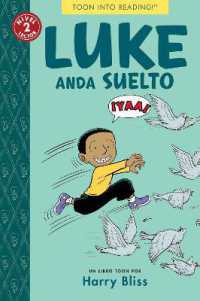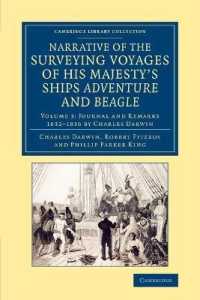出版社内容情報
『愛するということ』をはじめ幅広い著作を残し,幅広い読者を今なお獲得しているフロムだが,学問的にも不動の評価を受けているとは言いがたい。著者は,さまざまな精神分析家や哲学者・思想家たちとフロムを冷静に比較検討し,相違点と意外な共通点を探ってゆく。思想・心理学の領域におけるフロムの客観的位置づけをあらためて問う,貴重な試みである。
内容説明
人生と愛について深く洞察した精神分析界のアウトサイダー、エーリッヒ・フロムの仕事を思想史の中に位置づけなおす試み。
目次
1 人と仕事
2 フロイト‐マルクス主義と母権理論―初期の方法論的視点
3 フロムの臨床上の貢献
4 フロムの実存主義
5 社会的性格の研究
6 合意、同調、偽りの意識―「常態の病理」
7 心理学者、精神医学者によるフロムの評価
8 フロムの精神分析史への貢献
9 フロム‐マルクーゼ論争におけるエディプス・コンプレックス、本能、無意識
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ひつまぶし
2
精神分析家としてのフロムの業績を正面から検証する内容になっている。読んでいて分かりづらいのは、もはや精神分析自体が、分析視角としてはともかく、理論的根拠の怪しいものになってしまっているからだろう。性欲とか死の本能とか、生物学的な根源をたどる解釈には難があるとしても、パーソナリティを社会的性格と接続して文明論を展開したフロムの着想はそれとは別に再評価の余地があるのだと思う。心理学に吸収してしまっては損なわれてしまうものを、しかし、精神分析も汲み取りきれなかったからこその矛盾と衰退として受け止めなければ。2023/06/06