出版社内容情報
小学校体育科指導の最難関とも言われる器械運動「マット」「鉄棒」「跳び箱」の指導は、3ポイントと5ステップを押さえれば、どの子も「できた!」で笑顔いっぱいに!
新たに各技の解説動画(通常速度&スロー再生速度)を収録し、さらに分かりやすくパワーアップした器械運動の超定本!
体育がじつは苦手という先生でも、不安や悩みを抱えることなく現場指導できる具体的方法が学べます。
基本の技の指導法はもちろんのこと、安全を確保する補助の仕方、つまずいている子へのアドバイス、発展技や連続技への展開のさせ方など一挙収録!
どの子からも「できた!」を引き出すポイントが、分かりやすく学べる小学校体育科必携の本!!!
【目次】
Chapter1 器械運動の指導で大切にしたい10のこと
・何のために器械運動を学ぶのか?
1 単元計画を立てる
2 技のまとまりを教える
3 ポイントとステップを示す
4 グループを組む
5 場をつくる
6 安全を確保する
7 得意な子を飽きさせない
8 苦手な子を支援する
9 発表会をする
10 学びをふりかえる
・指導の流れ8ステップ
1 用意
2 準備運動
3 感覚づくりの運動
4 一斉指導
5 選択練習
6 全体確認
7 ふりかえり
8 片づけ
Column1 子どもの関わり合いを生み出すために
Chapter2 マット運動編
・ここを押さえればうまくいく! マット運動の指導法
・知っておきたい! マット運動理論:目線理論
・マット運動で指導する技一覧
・これだけはそろえたい! マット運動の準備物
・マット運動の感覚づくり
●前転
●後転
●壁倒立
●側方倒立回転
・マット運動の連続技
Column2 後転と髪型
Chapter3 鉄棒運動編
・ここを押さえればうまくいく! 鉄棒運動の指導法
・知っておきたい! 鉄棒運動理論:ふりこ理論
・鉄棒運動で指導する技一覧
・これだけはそろえたい! 鉄棒運動の準備物
・鉄棒運動の感覚づくり① 固定施設をつかったあそび(低学年)
・鉄棒運動の感覚づくり② 鉄棒をつかった運動
・鉄棒運動の感覚づくり③ 鉄棒のおり技
●さかあがり
●かかえこみ前回り
●膝かけふりあがり
●後方片膝かけ回転(膝かけ後ろ回り)
・鉄棒運動の連続技
Column3 さかあがりが全員できるようになるために
Chapter4 跳び箱運動編
・ここを押さえればうまくいく! 跳び箱運動の指導法
・知っておきたい! 跳び箱運動理論:ホウキ理論
・跳び箱運動で指導する技一覧
・これだけはそろえたい! 跳び箱運動の準備物
・跳び箱運動の感覚づくり
●開脚とび
●かかえこみとび
●台上前転(前ころがり)
●首はねとび
Column4 台上前転と跳び箱の種類
Chapter5 器械運動の指導と評価のポイント
・低学年の授業づくりのポイント
・中学年の授業づくりのポイント
・高学年の授業づくりのポイント
・「個別の知識や技能」の評価
・「思考力・判断力・表現力」の評価
・「主体的に学習に取り組む態度」の評価
Column5 課題別子ども先生
巻末付録●子どもの意欲がどんどん高まる! 器械運動のワークシート
内容説明
基本の指導法はもちろん、補助の仕方、つまずいている子へのアドバイスなど、イラスト&動画とともに一挙ご紹介!
目次
1 器械運動の指導で大切にしたい10のこと(何のために器械運動を学ぶのか?;指導の流れ8ステップ)
2 マット運動編(ここを押さえればうまくいく!マット運動の指導法;知っておきたい!マット運動理論:目線理論 ほか)
3 鉄棒運動編(ここを押さえればうまくいく!鉄棒運動の指導法;知っておきたい!鉄棒運動理論:ふりこ理論 ほか)
4 跳び箱運動編(ここを押さえればうまくいく!跳び箱運動の指導法;知っておきたい!跳び箱運動理論:ホウキ理論 ほか)
5 器械運動の指導と評価のポイント(低学年の授業づくりのポイント;中学年の授業づくりのポイント ほか)
巻末付録 子どもの意欲がどんどん高まる!器械運動のワークシート
著者等紹介
三好真史[ミヨシシンジ]
1986年大阪府生まれ。京都大学大学院教育学研究科修了。堺市立小学校教諭として16年間勤務し、現在は花園大学社会福祉学部専任講師。小学校から大学まで14年間、体操競技を続ける。器械運動指導を研究し、教員を対象とした研修を行っている。全日本学生体操競技選手権大会「跳馬」準優勝(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 電子書籍
- 今度こそ、この結婚を回避します~愛のな…
-
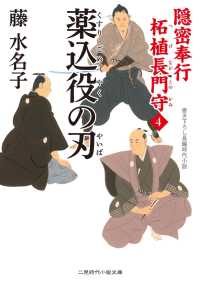
- 電子書籍
- 薬込役の刃 - 隠密奉行 柘植長門守4…





