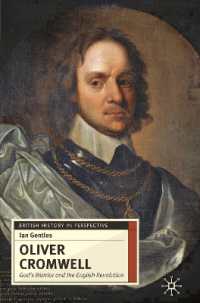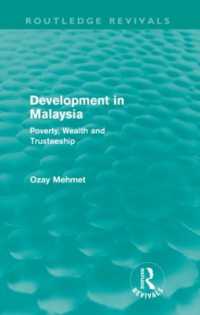出版社内容情報
ロシア語通訳者であり作家だった米原万里の、今さらに輝きを増す魅力に迫る。【エッセイ】沼野充義、亀山郁夫、斎藤美奈子。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
こばまり
46
没後11年の2017年に特別編纂されたムック。身近だった人の思い出話と著作解説。韓国で支持されているとは知らなかった。何故か我がことのように嬉しい。再読熱高まる。一つ前に読んだ本で紹介されていた多言語習得者ロンブ・カトーの著作を氏が翻訳していたとは。2024/08/18
おさむ
39
逝去されて14年になるのに、今なおファンが多い米原万里さん。毒舌ながら、物事の本質を突く慧眼と日本人には珍しいユーモアセンスの持ち主。そして「本に対して機嫌がいい人」発掘エッセイや対談もさることながら、友人や知人が彼女を偲んで語ったり、書いたりしている文章全てが愛情に溢れている。大学院で同窓だった河野通和さんや、通訳仲間のガセネッタとシモネッタ、プラハの小学生時代を共に過ごした小森陽一さんらのことばがあたたかい。彼女のような健全な批判・批評精神をもつ知識人が最近は減ってしまったのがなにより悲しい。2020/05/13
阿部義彦
34
本を読む事は「死んだ人と会話をする様なもの」と山本夏彦翁は仰ってました。私もこの本でまた新たな米原万里さんと出会う事が出来ました。連載した文章に圧力がかかって、書き直しや別な表現にして下さいと編集から言われても決して屈せずに、書き直しはしません、気に食わないのなら載せて貰わなくても構いません!と自分の意志を貫いた、何とも勇ましい事、兎に角空気を気にせずに、言いたい事を云う、ファンや昔添乗員だった頃の客から、親しげに話しかけられても、知らない事は覚えてませんとハッキリと言うそんな粗忽な所がまた魅力的です。2017/08/29
やまやま
22
巻末の略年譜から、20代までの激動と30代からの才能の具体的開花を改めて眺める。父の米原昶氏に連れられ9歳でプラハに行ったことで人生の方向が一つ定まったとは思えるが、ロシア語に留まらず、「真面目な」知的好奇心の強かったことは伺えた。同業者の沼野充義さんのエッセイは、自身編集のアンソロジーが好意的に受けなかったことの理由を語っているが、米原さんの指向の一つをよく捉えている。これも、大学院で一緒に学んだ縁もあって書けるレクイエムにも感じ、ただただ羨ましい。「真夜中の太陽」の由来は巻末に説明があります。2021/09/29
4fdo4
22
ご本人が亡くなられた後に出版された対談やエッセイをまとめたムック。 ものすごく魅力の詰まった方だったのだと、改めて思う。 長い物に巻かれない、自分の考えを強く持っていた素敵な人の発する言葉には魅力が詰まっている。 2019/09/01
-
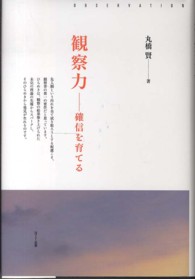
- 和書
- 観察力 - 確信を育てる