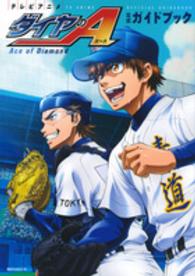内容説明
苛烈・残酷・凄惨な八大地獄の諸相と、仏教本来の地獄観から変容した日本人独特の死後世界観を解説。日本人の地獄観を形成した『熊野観心十界曼荼羅』を収録。
目次
第1章 因果はめぐる(地獄の絵画化;仏教の世界観;八大地獄;地獄の刑期;往生要集絵)
第2章 あの世の裁き(閻魔と十王;十王図と六道絵)
第3章 熊野観心十界曼荼羅の世界(熊野観心十界曼荼羅の図像;「家」と人生―新しい地獄観;熊野観心十界曼荼羅の特質)
第4章 地獄を絵解く尼僧―家と救い(熊野比丘尼;熊野の絵;地獄の絵解き;現生利益―破地獄と念仏)
第5章 流転する地獄絵(熊野観心十界曼荼羅の誕生;地獄絵の系譜)
著者等紹介
小栗栖健治[オグリスケンジ]
1954年生まれ。大谷大学大学院文学研究科修士課程修了。博士(文学)。専攻は日本文化史。兵庫県立歴史博物館館長補佐(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
きょちょ
30
地獄についていろいろと勉強になった。仏教の世界観というのは凄いなぁ。須弥山は知っていたが、我々が住んでいる世界は「せんぶ州」というところで地獄はその地下にあるという。八大地獄も知っていたが、地獄に落ちると途方もない時間責めさいなまれることになる。例えば1回串刺しにされても「活きよ」と言われ活きかえりまた串刺しにされる。閻魔大王だけでなく、十も王がいる。そしてそれぞれに仏がいる。すべての絵で「人間」はかなりちっぽけに描かれているのが何とも言えない。飲酒も地獄に行く罪の1つとは・・・(泣)。 ★★★★2018/08/01
花林糖
14
(図書館本)八大地獄、地獄の刑期、往生要集絵、閻魔と十王、各章のコラムが面白く読めた。熊野歓心十界曼荼羅の「こどもの地獄」が印象的。地獄絵の入門書的な本だけど結構内容は濃いめでした。2016/12/10
かふ
11
地獄絵の元になるのは源信(恵心僧都)『往生要集』からで『源氏物語』の横川の僧都のモデルとされるが『源氏物語』では地獄よりは極楽浄土の世界を説いている。貴族社会では極楽浄土を好んだのにその後庶民に下って地獄絵が盛んになったようである。その普及に熊野比丘尼がいて、彼女らが地獄絵の絵解きとして説法したという。当時女性の地獄落ちが多かったとされたというのは、そういう存在だったのだと思う。絵解きは熊野比丘尼の商売だからそれ以上話を聞きたければ金を出せということで地獄の沙汰も金次第という言葉が生まれたという。2024/04/26
blue_elephant
6
改めて仏教の世界観を知るにも良い。地獄の場所、大きさ、刑期までキチンと決まっていて面白い。確か、仏教は死んでもなお、あの世で修行して仏になるというが、死んでからも、まだ修行をしなくちゃいけないのは嫌だなあ〜と子ども心に思ったものだし、地獄絵を見せられたものなら、死んで地獄行きになったらどうしようと泣いたものです。時代によって、地獄の描き方も違うもので、現代なら謂れのない女性だけの地獄は無いのだろう。次は、澁澤龍彦の「地獄絵を読む」を観てみよう。2020/09/26
にしの
5
地獄絵の解説書。日本人の地獄観は大陸から伝わった十王教(閻魔さまとか)が往生要集の地獄と習合したもので、それが江戸期になるとイエと結びつき、民間信仰になっていったという流れらしい。民間信仰では学問的なものより町を練り歩き絵解きした熊野比丘尼(これで商売もしてたらしい)など民間伝承者の影響が大きかった。 僕の知ってる地獄はこんな風にいろんなものがミックスされてたんだなぁ!と感心。古事記とかに描かれてる黄泉の国は地獄とは別なんだな。あれは地獄より神や霊的なものに思う。空想が蔓延るなぁ。2023/06/28