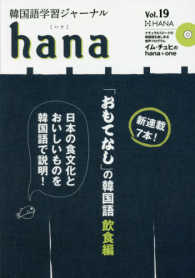内容説明
明治から現代まで、生活を変えた流行。モノで見る暮らしの移り変わり。
目次
はじめに 流行のいま、流行のむかし(移りゆく姿;オリンピックを迎えた東京 ほか)
第1章 あの味はここから―文明開化と食(東京発見;新しいものが勝ち ほか)
第2章 おめかしして、おでかけ―大正昭和の服・小物(キャンパス・スタイルブック;これがハイカラ ほか)
第3章 足りないという日常―戦時下の暮らし(文化的生活を送ろう;わが家の持ち物しらべ ほか)
第4章 それでも欲しい物―大量消費時代(洋服は便利だ;キッチン家電が新しい ほか)
著者等紹介
新田太郎[ニッタタロウ]
1968年、東京都生まれ。日本大学大学院文学研究科史学専攻博士前期課程修了。東京都江戸東京博物館学芸員
田中裕二[タナカユウジ]
1975年、北海道生まれ。法政大学大学院人文科学研究科日本史学専攻修士課程修了。東京都江戸東京博物館専門調査員
小山周子[コヤマシュウコ]
1976年、高知県生まれ。東京学芸大学大学院教育学研究科理科教育専攻広域自然科学・理科教育講座文化財科学分野修了。東京都江戸東京博物館専門調査員
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
氷柱
8
217作目。6月19日のみ。図書館本。個人的に卒論で書きたかったが、結論が締まらないものになりそうだということで没を食らったものをそのまま体現してくれたような作品。時代を表す流行物を取り上げてくれていて、戦後から現代までの少し細かい時代区分の流行りを垣間見ることができた。時代を表すものは服飾や日用雑貨である。こう手の文献は、娯楽の面が少し強く出ていることは否定できないが、一種の歴史の学習にもなる。たまにはこういった作品で知識を吸するのも良い。2016/06/19
ひねもすのたり
8
明治初頭から昭和が終わるまでの約100年。この間にブームになった物や風俗などをわかりやすく解説した本です。 この手の本はいくつも出ていますが、共著のお三方は江戸東京博物館の学芸員や調査員の肩書きをお持ちです。 そのせいか、ところどころアカデミックに突っ込んでいて、読物としても充分楽しめます。 上野の初代パンダのランランは剥製になってあちこちを廻っているそうです。 ご苦労様な話ですよね・・2014/03/09
富士さん
2
昔、バーゲンブックで買った本。やっぱりいい本です。考現学についでも本書で知りましたし、全体が生活史研究の成果だと思います。読み直して発見したのは、デパートはそもそもが安売店だったということです。大正期の着物も、昭和期のテレビも、良いものが安く手に入る小売店としてデパートは評価されていたというのです。それなら小売りの王様がデパートであっても当然というもの。いつからデパートはあんなにふつうのものを高く売るだけのお高くとまった存在に成り下がったのでしょうか。ほんのちょっと前のことですが、新たな発見があります。2025/03/22
takao
2
ふむ2021/07/26
めぐみこ
2
明治から平成の流行と生活について。文明開化~大正ロマン辺りが目当てだったのだけど、意外と戦時中の代用品の話も興味深かった。結局みんな本物の方を求めてた事とか、規制前にまとめ買いする事とか、現代にも通じるなぁ。小型ラジオ・パナペット70はポップでキャッチーで令和でも通用しそう。2020/03/16
-

- 和書
- 情報科教育法 (改訂)