出版社内容情報
新たな視点で語る「昭和の子ども史」。「楽しいこと」「哀しいこと」を豊富な図版で解説。「身売り」「人さらい」にも言及。
小泉 和子[コイズミ カズコ]
編集
内容説明
子どもがたくさん死んだ昭和戦前。昭和の子どもを包んだ「光」と「闇」。デパートの食堂、縁日、紙芝居。病気、貧困、戦争、学童集団疎開、身売り、もらい子殺し、人さらい。「楽しいこと」「哀しいこと」を豊富な図版で詳説。新たな視点で語られる「昭和の子ども史」!!
目次
巻頭口絵(楽しき子ども;哀しき子ども)
第1章 楽しき子ども(家族そろって楽しいお出かけ―デパートの食堂・屋上;街角では紙芝居;心おどる縁日と夜店;洋服で明るく元気に―「晴れ着」から「普段着」へ;おやつの時間;きょうだいの数)
第2章 哀しき子ども(子どもが死んだ昭和;身売りされる少女―新潟の例を中心に;人さらいとサーカス;生活記録に見る働く子ども;受難の学童集団疎開)
著者等紹介
小泉和子[コイズミカズコ]
1933年、東京生まれ。登録有形文化財昭和のくらし博物館館長。NPO法人昭和のくらし博物館理事長。重要文化財熊谷家住宅館長。家具道具室内史学会会長・工学博士。家具室内意匠史及び生活史研究家(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
yomineko@鬼畜ヴィタリにゃん💗
69
楽しいよりも悲しい事が多かった戦前~戦後すぐの子ども達。空襲、疎開、戦争孤児、人さらい、病気などで沢山の子ども達が犠牲になった。親がいて食べさせてもらえただけでありがたいとしみじみ思う。明るい話題もあり、何と16人ものお子様がいるご家庭が紹介されている。昔は10人は結構いた様で、戦後から2人きょうだいが定着して行ったらしい。グリコのおまけのレトロさ、細かさが凄い!ほしい!そしてデパートの屋上に遊園地というのはまるで夢みたいです✨2022/03/03
たまきら
44
昭和って長いんだよなあ…が、読後の印象です。死亡率も高く人身売買も珍しくなかったころ。戦後、高度成長期…。みんな「昔は良かった」っていうけれど本当にそうかな?しかしよくこれだけ多様な時代をこのページ内でまとめたなあ!すご~い。2023/03/13
きゅー
9
冒頭に「昭和戦前から戦中、戦後昭和20年代あたりまでは、子どもがたくさん死んだ時代でもある。子どもが死んだ昭和といってもよい。」と始まる本書は、昭和前期の子どもの暮らしを「楽しき子ども」「哀しき子ども」と大きく二つに分けて綴る一冊だ。「楽しき子ども」では、家族そろっての楽しいお出かけ、紙芝居、縁日、おやつ、きょうだい。「哀しき子ども」では、子どもの死、身売り、人さらい、働く子ども、学童集団疎開などに章立てられている。「哀しき子ども」パートの方がインパクトが強く、辛い気持ちにさせられる。2020/04/24
hitotak
7
縁日、紙芝居、デパートの屋上など今では廃れてしまった子供の楽しみと、病気、娘の身売り、疎開などの哀しい記憶が対照的にまとめられている。昭和30年代までの日本はまだまだ貧乏で、衛生状態や栄養不良で子供が亡くなることが珍しくなく、戦後直後くらいまでは育てられない生みの親から養育費を受け取った養親が乳児を殺すことも密かに行われていたなど、貧困ゆえにあらゆる点で子どもが犠牲になることが日常的だったようだ。楽しみの方も現代と比べれば素朴でつつましく、当時の子供たちがいじらしく感じる。2019/06/02
てくてく
4
昭和のくらし博物館の第14回企画展「楽しき 哀しき 昭和の子ども」をもとにした本。長い昭和期を圧縮しているので、特に戦前・戦後はかなり違うのではないかと思いつつも楽しく読んだ。第二次世界大戦前後の子どもが大量に死んだ時期が子ども史の中ではかなりイレギュラーではあるものの、今現在も子どもが大量に殺されていることを連想した。現場の教員や受け入れ側の献身的な対応はあったとは思うけれど、疎開というのは子どものことをあまり考えていない場当たり的なもののような印象が強くなった。2025/01/11
-

- 電子書籍
- 機動戦士ガンダム ヴァルプルギスEVE…
-
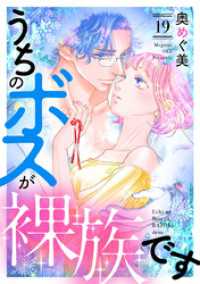
- 電子書籍
- うちのボスが裸族です(19) バニラブ


![エンジニア組織の英語化変革 EX[English Transformation]](../images/goods/ar2/web/imgdata2/42971/4297143437.jpg)
![パステル画家山中翔之郎猫カレンダー 〈2017〉 - モノトーンで描く愛猫元さんとなかまたち [カレンダー]](../images/goods/ar2/web/imgdata2/47755/4775525867.jpg)



