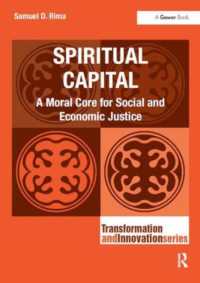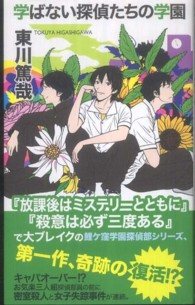内容説明
戦前・戦中・戦後の大激動期をけなげに可憐に生きた昭和の少女たち!!閉ざされた世界で「女子供」とおとしめられながらも育みつづけた少女文化。都市下層、農村、植民地、女子寮で、少女たちは何を学び、何を楽しみ、どう生きたのか?貴重写真満載!
目次
第1章 昭和を少女たちはどう生きたか(市民権を得た少女文化;裁縫とお稽古ごと―少女たちの学び;昭和の少女服装史;女子寮―女学校と工場;戦争を生きた少女たち;働く農村の少女―新潟県の場合;植民地挑戦の少女たち;都市下層の少女たち)
第2章 道を拓いた女性たちの少女時代(日本近代女性史のトップランナー―永原和子さん;女性漫画家の草分け―亀井三恵子さん;自然と人間が第一の建築家―富田玲子さん;高麗博物館設立に奮闘した―宋富子さん)
著者等紹介
小泉和子[コイズミカズコ]
1933年、東京生まれ。登録文化財・昭和のくらし博物館館長、家具道具室内史学会会長。石見銀山国指定重要文化財熊谷家住宅館長。工学博士(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
元気伊勢子
8
ここで言われている昭和は、近年語られている昭和30年〜60年代のことは書かれていないので要注意。少女、乙女たちのモラトリアム期間はとても短かった。しかもそれらを楽しむことができたのは限定された人達だけだったそうだ。可愛い文化に浸かりすぎて成熟を放棄するという記述にはハッとした。2021/11/25
きら
5
激動の時代、昭和。そんな時代、少女たちはどのような存在であり、どのような日々を過ごしていたのか。様々な視点から取り上げた一冊。 まだ男尊女卑の真っ只中、女はとにかく家を守って子供を産めばいいという時代のことは、さすがに隔世の感がある。そんな時代に、シスター系の学校では、上級生を姉と慕い、親密な関係を作るというマリみてのような世界が広がっていたというのがおもしろい。もともとは西洋から入ってきた文化なんだろうけど、半世紀前の日本とにわかに結びつかない。「かわいいカルチャー」への警鐘、ちょっと耳が痛いです。2013/09/13
かゆこ
4
東京都大田区鵜の木に「昭和のくらし博物館」という小さな博物館があります。その建物は、昭和27年に住宅金融公庫の融資を受けて建てられた、最初期の公庫住宅で、この本の著者、小林和子さんのご実家です。住宅地の中にある、とても奥床しい博物館ですが、昭和の暮らしが体感できる、稀有な場所になっています。貧富、都市と地方の格差社会、戦争、人種差別など、少女の生活から見える昭和という時代は、抑圧に満ちて、暗くて哀しい。昭和時代に興味のある方は、ぜひこの本を読んで、博物館にも足を運んでいただきたいな、と思います。
猫
4
昭和30年代くらいまでの、戦前・戦中・戦後のそれぞれの時代に少女として過ごした人たちの話。今を当たり前として生きている自分の目で見ると、男尊女卑で貧しくて、戦争の時代は厳しくて、つらいことが多く見えるけど、それが当たり前として過ごす目線で見える風景はまた違いそうだと、農村の少女として過ごした体験談を読んで感じた。 あと、個人的には朝鮮がらみの話は冗長かと。2014/09/22
コニコ@共楽
4
昭和を図鑑的に楽しめる本。といっても、戦前戦中の少女の暮らしは、楽しいことよりも耐え忍ぶものも多いことが記されている。その中で、健気に、あるいは逞しく生き抜く少女たちがそこにいた。随所に挟まれる「少女の名前」や「アンネの歴史」などのコラムも面白かった。2014/03/27