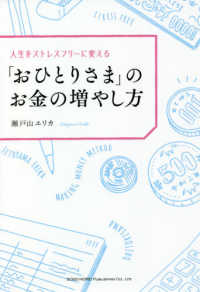出版社内容情報
【目次】
内容説明
お化け屋敷、おもちゃ、双六、手品、妖怪画、春画、黄表紙、映画、マンガ、ラノベ、ゲーム…遊びや笑い、大衆文化やフィクションに日本人の心性を読む―。これからの研究に不可欠な論考を集成した特選アンソロジー!
目次
総論 娯楽としての怪異・妖怪
1 娯楽と妖怪(化物屋敷の誕生;遊びの中の妖怪たち―近世後期における妖怪観の転換)
2 江戸の化物文化(素人の演出する怪談芸―江戸時代の「妖怪手品」について;豆腐小僧の系譜―黄表紙を中心に;化物と遊ぶ―「なんけんけれどもばけ物双六」;春画・妖怪画・江戸の考証学―〈怪なるもの〉の視覚化をめぐって;「妖怪」をいかに描くか―鳥山石燕の方法)
3 現代大衆文化と妖怪(通俗的「妖怪」概念の成立に関する一考察;「見世物」から「映画」へ―新東宝の怪猫映画;一九七〇年代の「妖怪革命」―水木しげる『妖怪なんでも入門』;鎌鼬存疑―「カマイタチ現象」真空説の受容と展開;ライトノベル異世界転生ものにおける異世界の生成―モンスターの和洋混淆状態を手がかりに)
著者等紹介
小松和彦[コマツカズヒコ]
国際日本文化研究センター名誉教授。専門は文化人類学、民俗学。長年、日本の怪異・妖怪研究を牽引してきた
香川雅信[カガワマサノブ]
兵庫県立歴史博物館学芸課長。専門は日本民俗学。博士(学術)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
佐倉
20
妖怪と言えば、な絵図のみのらずお化け屋敷、手品、玩具と様々な娯楽を取り上げていく。香川雅信が取り上げていた吉宗→田沼による諸国産物のカタログ化が江戸の妖怪ブームを生み出したのではないか、それは信仰とは真逆のパロディの対象としての妖怪だったのではないかという指摘、その流れで読める横山泰子の妖怪手品、アダム・カバットの豆腐小僧、岩城紀子の双六などとても興味深い。京極夏彦は妖怪という語の術語の側面/通俗性と近代/前近代の断絶と媒介を問う論考。紹介されていた多喜田昌裕の子啼爺研究も気になる。2025/10/30
Tanaka9999
13
2025年発行、河出書房新社の単行本。13編。正直、たまにはこういうのを読むのもいいね、ぐらいである。とはいえ江戸時代の怪談や怪異、現代の妖怪に関する論説と、なかなかに興味深い内容である。とはいえ深く理解しようとすれば疲れてしまうので、浅く理解する程度である。2025/10/05
わ!
10
第五巻は分野を問わないアラカルトだ。まず橋爪伸也さんの「化物屋敷の誕生」は再読。感想も書いた「化物屋敷」からの抜粋だが、これを読んでよくわかったが、抜粋された論文部分だけ読んでも面白いが、抜粋文を読んだ後でも元の本の面白みは残る様に考えている様である(「化物屋敷」の中核は抜けている)。「通俗的「妖怪」概念の成立に関する一考察」は、なぜ第一巻の「怪異・妖怪とは何か」に載せなかったのか不思議なぐらいによく出来た妖怪論だと思えた。あと妖怪双六や妖怪手品の話も楽しい。鎌鼬と豆腐小僧の謎は、まさにびっくりの内容だ!2025/09/17
ぞだぐぁ
1
「娯楽と妖怪」「江戸の化物文化」「現代大衆文化と妖怪」の3つの章に分けて別の本に収録された物や研究紀要、大学院の課題報告とかに載せられた論文を収録したアンソロジー。 妖怪が出ると生臭い風が吹くって話だけど豆腐小僧は精進なので例外とか、カマイタチ=真空現象説の広まりとか単にどうして妖怪が親しまれるようになったとかそういうのに留まらなくて面白かった。 インタビューした人の偏りとか混ざったりで実際はその地に根差した妖怪どころかそんなのあったの、と現地の人すら思っている物なんかは調査の仕方の問題にも繋がって(続く2025/11/21