出版社内容情報
若者たちのリアルと大人たちの視線とが交わってはズレてゆく、80年代からの軌跡。自己の「多元化」の実像を更に追究する章を増補。
【著者紹介】
1964年生まれ。東京学芸大学教授。専門は社会学(自己論・物語論・若者文化論)。『趣味縁からはじまる社会参加』『自己への物語論的接近』など。
内容説明
若者たちのリアルと大人たちの視線とが交わってはズレてゆく、80年代からの軌跡。オタク、自分探し、「個性」教育、ひきこもり、キャラ…補章「拡大する自己の多元化」を追加収録―最新調査から見えるアイデンティティの現在とは?
目次
第1章 アイデンティティへの問い
第2章 それは消費から始まった
第3章 消費と労働との間で
第4章 「コミュニケーション不全症候群」の時代
第5章 コミュニケーションの過少と過剰
第6章 多元化する自己
第7章 多元的自己として生きること
補章 拡大する自己の多元化―世代・時代・年齢
著者等紹介
浅野智彦[アサノトモヒコ]
1964年、仙台市生まれ。東京大学大学院社会学研究科博士課程単位取得退学。現在、東京学芸大学教育学部教授。専門は社会学(自己論、アイデンティティ論、物語論)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
きいち
28
若者論に留まらない、「多元的な自己」論の決定版。◇学生時代に初めて自己同一性という言葉を知った時、アイデンティティは統合するもの、拡散してたら失敗ってのがどうも受け入れられなかった。局面局面で異なる自己、あって当たり前じゃないのか、と。アイデンティティ論はいくつも読んできたけれど、自己の多元性にポジティブな意味づけをしてくれたのは初めてじゃないか?人間関係や感情労働のリスク回避は今を生きるのに不可欠の技術だもの。◇エリクソン、リースマン、ギデンズ、バウマン、整理はとてもありがたい。◇01-11比較を増補。2016/04/30
ひつまぶし
2
若者論自体が現代社会のアイデンティティ論だったという視点からの考察。若者が問題化されるのは若者を発見する側の都合であり、問われていたのはアイデンティティであったとも言い換えられる。消費社会化する中で多元化する自己に注目が集まったわけだ。アイデンティティは普遍的なテーマではない。しかし、この問いから逃れられない状況もある。これが現代社会のコスモロジーの一部を成しているとも言えるだろう。するとそこには数々の神話が生まれてくる。まずは神話を語らなければならず、次に神話であることに気づかなければ理解もできない。2024/11/27
ながしま
0
仕事の参考に読みはじめたが、読んでるうちに10代・20代だった頃の自分を思い出し、自分ごととして読んでしまった。30年間での社会の変化はかなりのものであると思うし、「若者たちは誠実さをできるだけ損なわずにこの社会を生きていくためにキャラという様式を選び取る」という指摘も確かになぁと感じた。やっぱ今の時代フットワークの軽さって大事なんだろうな。2018/09/27
-
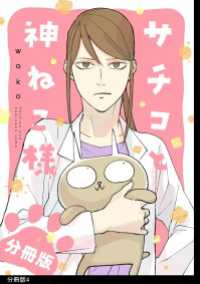
- 電子書籍
- サチコと神ねこ様【フルカラー】分冊版(…








