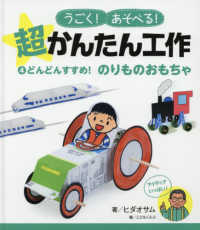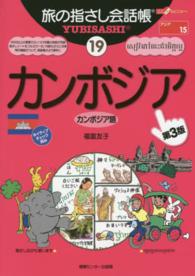内容説明
平氏と源氏が勢力を争っていた時代、奥州藤原氏は、いかにして勃興し、東北の覇者として君臨できたのか。また、平泉はなぜ“黄金の都”として繁栄できたのか。かの地に脈々と息づく精神風土から掘り起こし、その実相に迫る。
目次
1章 奥州藤原氏にも受け継がれた精神風土をさぐる―古代東北には、なぜ独立した王国があったのか
2章 朝廷の東北支配を揺るがした「前九年の役」をめぐる情勢―藤原三代の祖・経清と源頼義との壮絶な戦いとは
3章 「後三年の役」から奥州の支配権確立まで―初代・清衡は、いかにして“黄金の都”平泉を造ったのか
4章 「保元・平治の乱」から平氏全盛期まで―都での勢力争いに乗じて繁栄した三代・秀衡の戦略とは
5章 源平争乱と平氏滅亡で迎えた転換点―源頼朝と対立する義経は秀衡と、どんな関係にあったか
6章 奥州征伐による藤原政権滅亡と、その後の平泉―奥州一〇〇年の栄華はなぜ終幕を迎えたのか
著者等紹介
武光誠[タケミツマコト]
1950年、山口県生まれ。東京大学文学部国史学科卒業。同大学院博士課程修了。文学博士。現在、明治学院大学教授。専攻は、日本古代史、歴史哲学。比較文化的視点を用いた幅広い観点から日本の思想・文化の研究に取り組む一方、飽くなき探究心で広範な分野にわたる執筆活動を展開している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
やま
85
11世紀半。陸奥国で起こった「前九年の役」、その後に起こった「後三年の役」が思い起こされます。本やNHKの大河ドラマで小さい時から頭に刷り込まれています(笑) 驚いたのは奥州藤原氏が、本拠を奥六郡の南方の磐井郡の平泉に置いて南方進出を狙っていたことです。そこは陸奥国府の多賀城から60キロしか離れていません。それとともに京都との交易を重視していました。砂金が採取され。また平安時代半ばから、奥六郡は良馬の産地として注目され。京都でも関東地方でも高値で取引されていました。字の大きさは…小。★★★☆☆2021/09/05
翔亀
46
東北の独立王国/世界遺産平泉。こう聞くと想像を逞しくする一方で所詮貴族のエピゴーネンではないかと勝手に思い込んでいたが、五味文彦さんの濃密な『中世社会のはじまり』がページを割き、「東方の仏国土の支配者」(清衡)から「京の王権を模した奥州の支配者」(基衡)への変化や西行の歌、最近の発掘の新発見などを知り、俄かに興味を抱き、奥州藤原氏の入門編として紐解いてみた。縄文時代の東北から鎌倉幕府誕生までの日本史の流れの中で、奥州藤原三代が位置づけられ、入門編としては最適。義経伝説を始めとした説話を紹介しながら楽しい↓2017/05/16
金吾
20
奥州藤原氏のことがわかりやすく書いています。前九年の役と後三年の役がスッキリしたのは良かったです。また源平の争いの時の独自性も良かったです。2024/09/06
たひ
1
それほど難しいこともなく読めました。読みやすい。2019/03/31
-

- 電子書籍
- アオバ自転車店(19)
-

- 和書
- 維持更新時代の公共投資